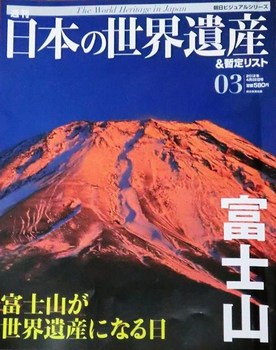宮城・気仙沼で見つけた天才少年、段ボール彫刻作家が心をなごます
東日本大震災の被災地・気仙沼の市街地で、通行人が「おやっ」と足を止める光景がある。
それは海産物問屋の店頭で、段ボール箱を組み立てたロボットが堂々と突っ立っている。それは誰が見ても、あきらかに子どもの作品だが、くすっと笑ってしまう。

㈱勝正商店は気仙沼駅から海岸の向う途中の、三日町交差点の角に位置する。信号待ちする乗用車の車窓からも、
「ほら、見て、みて」
と指差す光景がある。
年少者が制作したもので、海産物の空いた段ボール箱を利用したものだ。ユーモラスな作品だ。
気仙沼は1000人以上の死者と行方不明者を出した、悲惨な被災地である。1年余りが経ったいま、ガレキの撤去は進んできたが、都市再生や復興は遅々として進んでいない。市民の多くは心に傷を負ったままで、口には出さないが、暗い気持ちである。
それだけに小学校1年生の斉藤勝市郎くん(さいとう しょういちろう・6歳)の作品が、行きかう人の心を思わずなごませるし、明るい話題の提供となっている。
三日町1丁目は、3.11の大津波が床下まできた地域だ。全壊の家屋が少なかっただけに、商店や会社などは順次営業を再開してきている。
勝正商店も同様である。オフィスと作業場が隣り合い、営業活動が行われている。これら海産物の袋詰めとオフィスワーク(家族5人と社員5人)が、通行ちゅうの人たちからものぞきこめる。
そこには『段ボールの時計台』とか、『発泡スチロールのお城』とか、『三階建てマンション』とか、さらには絵画など、勝市郎くんの制作品が所狭しと展示されている。
どの作品も箱の立体空間を上手に利用している。
店内で、勝市郎くんの創作について話を聞いた。
「通行人の方が笑ったり、面白い、愉快だと足を止めてくれるんですよ」
祖母が町の人気者だと教えてくれた。
三陸地方は過去から海産物で栄えてきた。漁業の産地からは段ボールで商品が送られてくる。同店では作業場で小割して袋詰めする。
毎日、決まって空箱が出てくる。勝市郎くんはそれら形状を見た瞬間に、何が作れるか、イメージがひらめくようだ。
「毎日、なにかしら作っています。カッターやナイフは危ないので、使わせていません。すべてハサミです」
と母親が話す。
「働く人、全員にケータイのストラップを作ってくれたんですよ」
母親がそれを見せてくれた。それぞれ(10人の)顔の特徴がとらえた動物に似せる、ユーモラスな絵が飾りになっている。