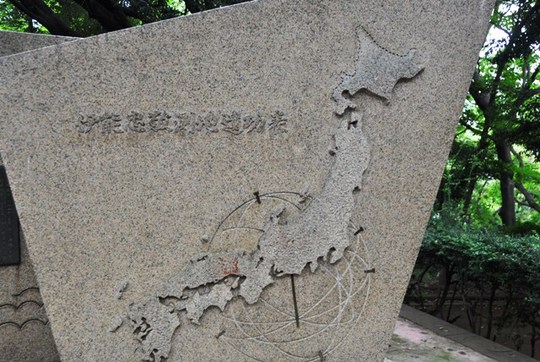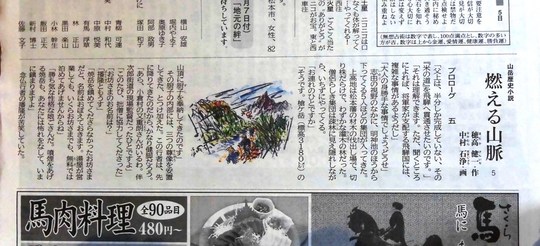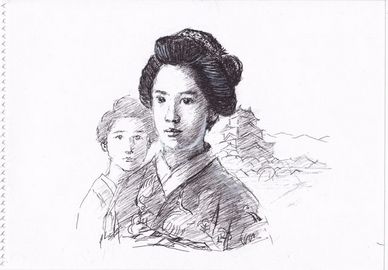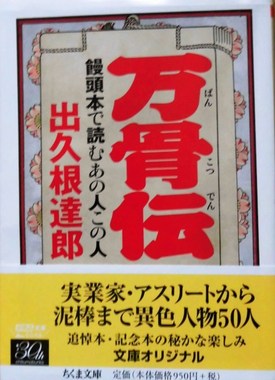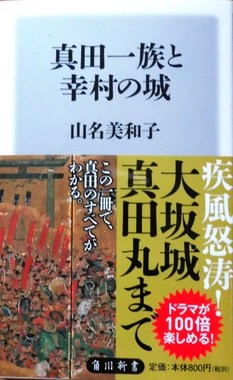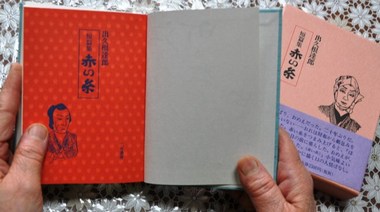第93回 元気に100エッセイ教室 =テーマの絞り込みについて
エッセイでも、小説でも、
「この作品のテーマは何ですか」
そう質問すると、作者が着想を語ったり、素材を語ったり、あらすじを語りったりする。
テーマとは何か、それ自体がわかっていないからである。
 エッセイなどは、まだ枚数が少ないから、勢いで読まされてしまう。小説など400字詰め原稿用紙に換算し、30枚、50枚、100枚となり、テーマの定まっていない作品など、とても読めたものではない。苦痛だし、「世の中には、読みたい作品はいくらでもあるんだ。これを無理して読む必要がないんだ」という気持ちにさせられる。
エッセイなどは、まだ枚数が少ないから、勢いで読まされてしまう。小説など400字詰め原稿用紙に換算し、30枚、50枚、100枚となり、テーマの定まっていない作品など、とても読めたものではない。苦痛だし、「世の中には、読みたい作品はいくらでもあるんだ。これを無理して読む必要がないんだ」という気持ちにさせられる。
「独りよがりの作品など、書いてはだめだよ」と、私は指導する読売カルチャー・金町「文学賞を目指す小説講座」、目黒学園カルチャー「小説の文学賞を目指そう」で、講師としてわりに辛辣に指導する。
余談だが、先月に50枚の中編で、上記・目黒学園の受講生で、文学賞を獲得した女性がいる。作品の狙いがはっきりしていたからだろう。
多くの作者は、こんな悪い例から、作品を書きだす。
「これは受けるはずだ」
と作者が思い込み、書きはじめる。
しかし、テーマが決まっていない。しだいに話がまとまらず、収集がつかなくなる。あげくの果てには頓挫してしまう。
あるいは登場人物が多すぎたり、話が飛んでしまったり、脱線したり、無駄なものまで書き込んでしまう。
結果として、エピソードは興味深いけれど、いったい作者は作品を通して何を言いたかったのか、よく解らない。書き出すときには、作者の頭のなか(着想)は良品でも、作品にすれば、アイデア倒れの駄作になってしまう。
叙述文学(エッセイ、小説)を目指す人は、徹底して、「テーマ研究」を行わなければ、少なからず、他人がお金を出して読みたくなる作品はかけない。職業人として物書きになるならば、常に「斬新なテーマ」を追い求める必要がある。
そもそもテーマとは何か。それがわかっていないと、プロになる手前で、お払い箱になってしまう。それほど「テーマとはなにか」は、重要だ。
(悪い例)「この店舗は立地が良いが、従業員は不潔な身だしなみだ」(着想)
勤め帰りの私は、駅前の惣菜屋に立ち寄った。餃子を買った。店員の白衣が汚れているから、手や指先までも汚く見える。他の客もきっと同じ気持ちだろう。こんな従業員はやめさせられないのかしら。……作文調であり、テーマは何か、読者にはわからない。
(悪い例)「知人の展覧会はよかった。エッセイに書こう」(着想)
電話で友人を誘うと、当日はヒマだという。最寄駅で待ち合わせをしてから、展覧会の会場に入る。割に混んでいた。知人の風景画は素晴らしいと、友人とお茶しながら感動を共有した。……単に、絵画鑑賞の流れにすぎない。
では、「テーマ」とはなにか。作者が言いたいことを、一言の文章で言い表せるものである。
【明確なテーマ】
「口論もない夫婦には愛がない」
「一途な想いほど、結婚後は失望へと変わる」
「老夫婦は過去の憎しみまでも流せる」
※ これらテーマが決まれば、それを最後の一行にテーマをおく。こうした流れで結末に向かって書いていけば、良い作品が生まれます。〈最大のポイントです〉
【実例】
かれは帰路の道々、愛に燃えていた季節は二度とよみがえらないと思った。いまは惰性か、失望か。婚前に燃えすぎると、落差が大きいな、としみじみ思った。親の言いなりにいやいや結婚した人間のほうが、いまは家庭内で、親子ともども生活をエンジョイしていると思えて仕方ない。
帰宅して玄関鍵をじぶんの手で開ける。この瞬間の空虚な気持ちはなんだろう。結婚後の甘い生活は過剰かたいだったのか。キッチンで水を飲み、寝室の戸を開けた。
いつもながら、お帰りの一つもない。問いただせば、妻なりの言い分がある。もう、それも疲れてしまった。
妻の寝顔を見ながら、「一途な想いほど、結婚後は失望へと変わる」と彼はつぶやいた。
ラスト一行が成立するような、ストーリーを組み立てればよいのだ。必要枚数で、登場人物の数を決めていく。
『頭のなかは名作、書けば駄作』
これは、テーマをしっかり抑えて書くだけの力量のない、素人筆者への格言である。