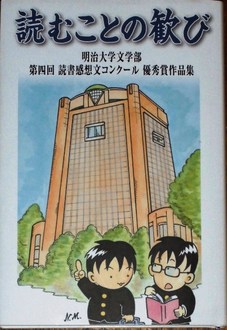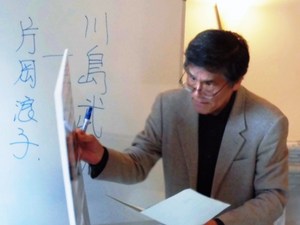プロから学べる、感動できる「2012年報道写真展」=東京・日本橋
東京・三越日本橋本店の7階で、第53回2012年報道写真展が開催されている。主催は東京写真協会。テーマは「熱狂、興奮、感動の瞬間がそこにある」。12月24日(月・振替)まで。
トップを飾る写真は、8月20日に、五輪メダリストのたちの銀座パレードに50万人が集まった(報知新聞社)。この迫力は同展のポスターにもなっている。

私は、プロ野球の選手がファールボールを追って、スタンドのカメラ席に顔面から落ちている。この一瞬の撮影はすごいな、と感銘した。報道陣のど真中に選手が(飛び込んで)落ちてきている。逃げるカメラマンの様子が捉えれている。当該記者はカメラを向けて撮っているのだから、まさにプロ中のプロだと思う。
香港の民間反日団体の船が尖閣諸島の魚釣島に接近してきた。わが国の巡視船2隻が航行しながら、香港船の船体を挟み撃ちにしている。1枚の写真から、海上保安官たちの操船技術の高さが如実にわかる。と同時に、尖閣諸島の緊迫度が写し出されている。
「東日本大震災から約500日」のサブタイトルでは、被災直後の写真と現在とを組み合わせたものが多かった。写真の前で、ハンカチを出して、涙をぬぐう人もいる。
フクシマ原発の原子炉建屋の公開では、ガレキ化した建物のなかから、円筒形の黄色い格納容器のふたが見えている。不気味さが伝わってくる。
 スポーツ関連の写真はオリンピックに、とくに注目が集まっている。立ち止まる人も多い。感動の呼び起こしだろう。
スポーツ関連の写真はオリンピックに、とくに注目が集まっている。立ち止まる人も多い。感動の呼び起こしだろう。
最新の写真は、衆議院選挙で大勝した自民党の様子である。報道関係だけに、やることが早いな、もうパネルで展示されている、と思わせた。
今年亡くなった著名人の顔写真も数多く並ぶ。一世を風びした人も、やがて死に行くのだな、と生命の滅亡に寂しさを感じさせる。
作品総数は250余点である。
同展から技術を学ぶとすれば、「決定的な瞬間と偶然とは違う」、事前の予測も必要だな、と思わせた。オリンピック会場の報道写真家はまさにメダリストの表情狙いである。企画的な写真にはハイアングルとか、ヘリコプターからの高所撮影が効果的だと思わせるものが多かった。
ニコン、キャノンの報道陣が使う、高性能カメラが触ってシャッターが押せる。連写の早さには驚かされる。だが、なぜかしら手をふれる人は私が見ているかぎり誰もいなかった。あまりにも高級すぎで、無縁だと考えているのだろう。