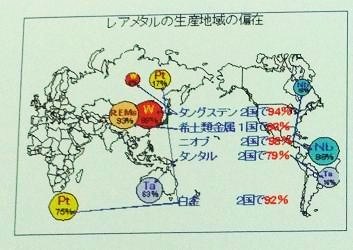【寄稿・小説】 森田哲郎「最高の夕食」
額の汗をハンカチでぬぐいながら、駅ビルを登る。待ち合わせの時間までは十分余裕があるが、急ぐに越した事はない。妻の友人のつてでコンピュータ会社へ中途採用の口ができたのだ。今日は最終面接らしい。
不況のこの時勢、必要なのは人とのつながりだと実感する。もうこれであてのない履歴書を書く必要はないのだ。
待ち合わせ時間ぴったりに来た妻の友人は、僕と目を合わすと気まずそうな顔をした。嫌な予感がした。
「非常に申し訳ないのですが」
派遣先との調整がうまくいかず、募集人員が削減されたらしい。彼は淡々と事情を話した。僕には文句の言える筋合いはないので、じっと聞いているしかなかった。職を得られなかったというのに、彼の誠実さに関心してしまったくらいだ。
しかし、明日からどうやって生活していけばいいのだろう。三十代に入ると、募集は激減する。二十代に数年、腰掛けでサラリーマンをしていた僕にとって、再就職は難関である。求人誌を読みながら、何か取り返しのつかない状況になったと思ってしまう。
以前、ささいなことで会社を辞めてしまった。それを後悔しはじめるのである。一度そのことが頭をよぎると他のことを考えられなくなる。気分は悪くなり、些細な妻の言動にも腹を立てるようになり、喧嘩をする。
そんな状況だから、妻が提案してくれた今回の話は願ってもいないことだった。すべてが好転すると思っていたのに。また妻に八つ当たりする僕になるのだろうか。そんな弱さにかなり落ち込む。しかも僕は酒がまったく飲めないので、アルコールで気を紛らわすことさえもできない。もっともアルコールを飲んでも事態が変わるわけでもないから、幸いなことかもしれないが。
アパートに帰るのが億劫になった僕は、別れると、階下にある本屋に寄った。まず僕が向かうのがベストセラー作家のコーナーだ。そのなかでも僕は分かり安い物語を好む。あまり小説で深く考えさせられたりするのは苦手なのだ。ただでさえ毎日頭を悩ませているのに活字を追ってまで落ち込みたくない。
僕が手に取ったのはスパイアクションものだった。洒落た文体で、逆境に置かれた主人公の強さが語られていく。