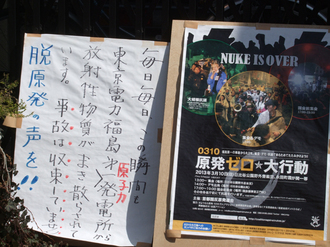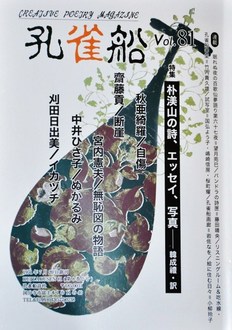【読書・感想】 海は憎まず=濵﨑洋光
小説3・11「海は憎まず」のご出版おめでとうございます。書店で品切になる好評のご様子、何よりです。拝読した私の感想を述べさせていただきます。
2011年3月11日、机に向かって書き物をしていた私は、その時、小刻みな振動を感じた。と同時に、これまで経験したことのない激しい揺れが家全体を襲った。それが東日本大震災だった。
多くの死者と大きな災害をもたらし、千年に一度ともいわれている。この自然災害の恐ろしさを感じなかった人はまずいないだろう。当時、マスコミは被災地の状況を連日大きく報じていた。

「海は憎まず」の著者・穂高健一さんは、それらの報道に満足せず、津波災害に焦点を絞り、自分の目と耳で、被災地、被災者の実像に迫った。
作中の主人公「私」が、インタービユした相手は老父を介護する一庶民から、地域の治安を守る警察署長など、多岐にわたる。取材された場所は、宮城県名取から岩手県陸前高田で、津波災害が大きかったところだ。
そこで語られた被災者の話には虚飾や誇張が感じられない。作者の表現の巧みさに引き込まれて読み進んだ。人間の生きるたくましさを感じる。とくに藤原中学校長が、
『教員は生徒に夢を与えるのが仕事です。被災は生徒にとって、心の財産なんです。それを引き出すことです』
という冷酷なまでに冷静、そして未来を見つめる言葉には感動されられた。
津波災害が発生した時の気仙沼警察署長の話は、警察の任務遂行と部下の生命を守る、という組織の長としての苦悩が胸を打つ。
その時、警察組織で重要な情報システムの喪失を知り、読者の私は背筋が寒くなる思いをした。それは私だけだろうか。そのうえ、災害直後から、町は無法地帯化していくのだ。
人間は自然とともに生きている。どんなに危険な土地であろうとも、そこに生きようとする。
災害の翌日から牡蠣(カキ)の養殖に励む。人間は大自然に抱かれて生きているのだ。しかし、ときに自然は牙をむき人々に襲いかかる。
小説は女性カメラマン彩との三陸取材の物語として流れる。身近な彩が連れ合いを二度事故で亡くしていた。人間は自分の過去、とくに辛かった過去を容易に口にしないものだ。主人公の「私」が執拗に訊いても、彩は思い出したくもない態度をとり続けてきた。
やがて彼女の口から、 離別の体験が語られた。辛い心証を小説家に打ち明けた彼女だったが、それを超え、なおも三陸の津波被災者の取材に協力していく。「彩の物語」としても描かれているのではなかろうか。
一読者として、そのストリーが女性心理の一端を突いていて面白く読めた。
「海は憎まず」には、巨大津波被災者からの多くの教訓が描かれている。一人でも多くのひとに読まれて、自然との共生を考える絆となればと思った。
濵﨑洋光さん:「元気に百歳クラブ」のエッセイ教室の元受講生