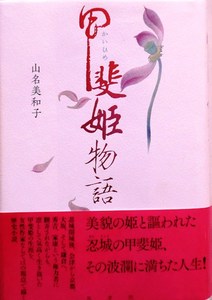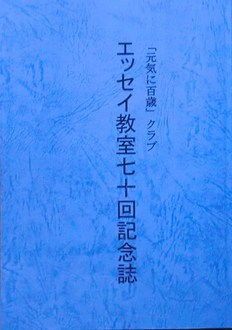「今回は遅刻しなかったわね。穂高さんは」と山名さん(歴史小説作家)さんにいきなり、言われた。もし遅れたら、置いていくつもりだったのよ、と彼女はつけ加えていた。小、中、高校の教員歴があるだけに、時間の躾(しつけ)? には厳しい。
この年齢にして、もはや遅刻魔の私の修正は治らないだろうな。
8月7日12時半に、浅草橋に集合だった。改札口には文学仲間の全員がそろっていた。むろん、私の到着がビリである。
「歴史散策」は8回目となった。山名さんのほかに、井出さん(日本ペンクラブ事務局次長)、吉澤さん(同事務局長)、新津さん(ミステリー作家)、相澤さん(作家)、清原さん(文芸評論家)、そして私を含めた7人である。
外気温は連日の35度前後である。
真昼間の長時間の街歩きとなると、話題はとかく熱中症対策になりがちだ。「暑い、暑い」と言ったところで、涼しくなるわけがない。水分補給は必要だが、飲むほどに汗が流れ出てくる。日陰は少ないし、街角の自販機をつい横目で見てしまう。

柳橋は、時代小説には欠かせない場所だ。粋な姐さんの柳橋芸者が現れる。過去に読んだ、池波正太郎、海音寺潮五郎、山本周五郎など多々の作品が断片的に思い浮かぶ。その情感を味わってみる。
小説では、夕暮れの情感を誘う小料理屋の描写も多い。それらしき割烹、小料理屋の店頭をのぞく。いずれも料理の値段は高そうだな、と現実に戻ってしまう。
神田川と隅田川の合流点には、複数の屋形船が浮かぶ。屋形船の櫓の音がぎー、ぎーと川面に流れる、こんな夏の夕涼みの情緒は、江戸時代の小説に数多く描写されている。
平成23年の真夏の昼間となると、どの船上にも船頭の姿はなく、ただ係留しているだけだった。
 「薬研掘り」。響きがとても良い。
「薬研掘り」。響きがとても良い。
吉沢さんと新津さんが名物の唐辛子を買う。店頭の女将さんがていねいに量り売りをしていた。「七味」と「一味」と、どう味が違うのだろうか。
鍋料理とか、うどんとかに振りかける、という認識ていどの認識だ。味覚として、唐辛子の味にこだわったことがない。唐辛子の風味まで感じ取れないと、本ものの食通とは言えないのだろう。
両国散策コースは、わりに社寺仏閣が少ない。両国橋にさしかかる。東京スカイツリーが、隅田川の対岸に屹立する。ここらがいまや東京の名所になっている。
眼下の川面には観光の水上バスが行きかう。タグボートがヘドロを積んだ台船を弾く。橋を渡り終えると、話題は「両国国技館」になった。
幼いころ遊びが限られていた世代だ。そのころは学校の砂場で相撲をとる。夕刻には、ラジオの大相撲にじっと耳を傾けていた。それぞれが想い出の一コマとして相撲人気時代のエピソードを語る。決まって栃錦、千代の富士など往年の名力士の名まえが出てくる。
勝海舟の出生の碑とか、芥川龍之介の文学碑とかがある。芥川は両国高校から東大に進んでいる。生れもこの近くだろう。
忠臣蔵で名高い、吉良邸があった。邸内には、「吉良の首洗いの井戸」と表記がなされていた。
「この井戸怖い」と新津さんがそれでも覗き込んでいた。ミステリー作家らしい好奇心だ。
回向院に入った。歴史小説家・山名さんが説明してくれる。1657(明暦3)年に開かれた浄土宗の寺院。「振袖火事」の名で知られる明暦の大火災では、江戸市街地の6割以上が焼土となった。10万人以上の尊い人命が奪われたという。
 ネズミ小僧次郎吉の墓がある。黒装束姿のネズミ小僧は闇夜に大名屋敷から千両箱を盗み、貧しい長屋に小判をそっと置いて立ち去ったと語られている。
ネズミ小僧次郎吉の墓がある。黒装束姿のネズミ小僧は闇夜に大名屋敷から千両箱を盗み、貧しい長屋に小判をそっと置いて立ち去ったと語られている。
江戸が東京となった現在でも、義賊のネズミ小僧はヒーローである。境内のネズミ小僧の墓石を削り、「お守り」に持つとご利益があるようだ。受験生が「合格祈願」で墓石を削り、受験会場に持ち込む、という。
吉澤さんが、墓前に用意された小刀(?)で、墓石を削り、有難がっていた。どんなご利益を期待しているのだろうか。聞くだけ野暮だ。
大相撲博物館の前は素通りし、「江戸東京博物館」に入った。歴史が得意のメンバーだから、みな何度か足を運んでいる。いまはひたすら暑さから、逃げ込んだ感じだった。
館内ではたっぷり2時間ある。(飲み屋が開店となる5時から逆算して)。特別展、常設展はじっくり見ることができた。
常設展の撮影はOKだが、フラッシュは禁止。復元された町並みの模型は見るほどに楽しい。気持ちが入り込み、時代小説作家の、藤沢修平、伊藤桂一などが描いた、江戸の情景の場面と重ね合わせる。
続きを読む...
 作者はつねにマンネリを打破する心がけが大切です。それには「どう書くかよりも、内面の何を書くか」と考える。辛くて、勇気がいる、そういう作品ほど、書き終えると、喜びと充実感を覚えるものです。
作者はつねにマンネリを打破する心がけが大切です。それには「どう書くかよりも、内面の何を書くか」と考える。辛くて、勇気がいる、そういう作品ほど、書き終えると、喜びと充実感を覚えるものです。