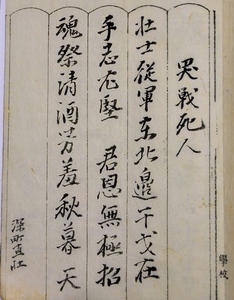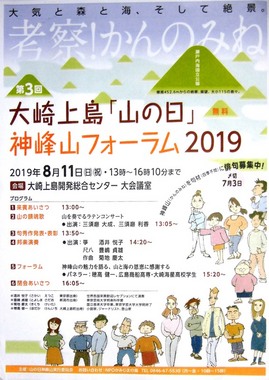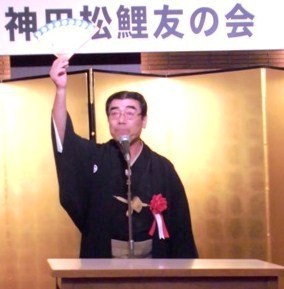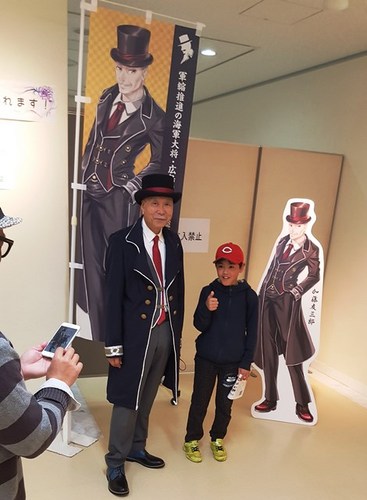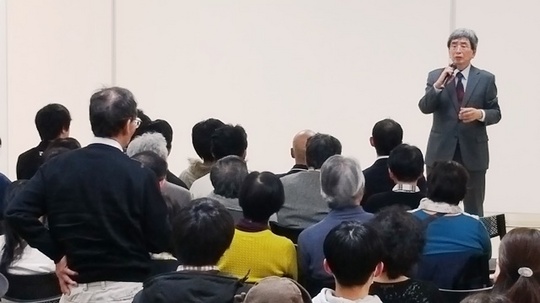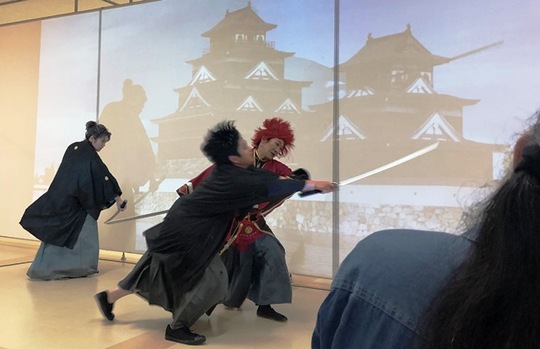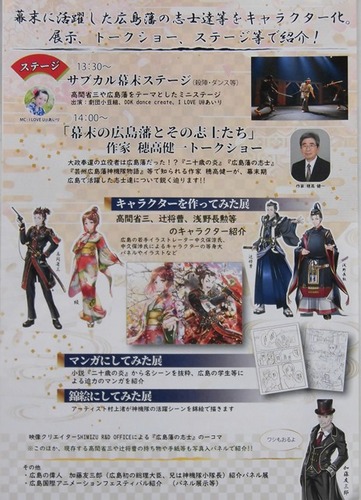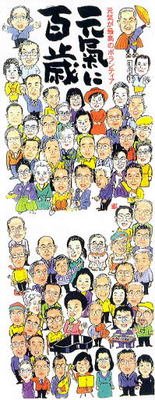日本上空は誰のもの。戦争の火種にならないか=歴史的な史観より
戦争は大半が隣国との争いから起こっています。初期のころ、火種はまさか大戦争になるとは予想できないものです。
第一次世界大戦は、オートリアの皇太子が、サラエボで一人の青年に射殺されたことが発端です。空前の9000万人以上の軍人が動員されました。終戦処理の問題からナチスドイツの台頭があり、21年後にして、またしても第二次世界大戦が起きました。
「あなたは、日本が近い将来、もし外国と戦争するとなれば、どこの国が予測されますか」
こんな質問をむけると、多くの人が怪訝(けげん)な顔をします。別段、平和ボケを批判するつもりはない。ただ、危機管理は必要だし、戦争の火種はつねに消す努力する必要があります。
尖閣がらみで中国、竹島にからんで朝鮮半島、北方四島の問題でロシアですか。
「米国と戦争する可能性が、最も高いのですよ」
というと、
「えっ。そんな馬鹿な」
という評定をされるか、一蹴されてしまう。
 日本の上空はアメリカ軍が支配しています。太平洋戦争の終了後も、日本の上空の制空権は奪われたままです。つまり、横田、三沢、岩国、那覇など、制空権はアメリカ軍にあり、私たちの上空は植民地のままです。
日本の上空はアメリカ軍が支配しています。太平洋戦争の終了後も、日本の上空の制空権は奪われたままです。つまり、横田、三沢、岩国、那覇など、制空権はアメリカ軍にあり、私たちの上空は植民地のままです。
東京オリンピックを前に、羽田空港の新発着ルートが拡大する予定です。ただ、横田基地の制空権(横田空域)があり、狭い幅のなかで、かなり無理した飛行が求められます。
新宿の高層ビルの上空、渋谷の繁華街、東京タワーの横から、羽田空港へ急角度で進入してきます。
富士山の横から広々とした進入路をとれない。それは厚木空軍基地があるからです。米軍空母と行き来する艦載機のルートがあり、わが国の空でありながら、日本の民間機が独自に利用できないのです。
私たちの記憶から消えていないのが、羽田発の日本航空の御巣鷹山事故です。尾翼の故障だったという。大惨事でした。
羽田新ルートで、嵐、風雨、霧、夜間、鳥など、万に一つの事故。管制塔とのITの不備、海外から飛んでくる飛行機も含めて、パイロットの過労、格安飛行機のコストダウンからの整備不良などから、国内外の旅客機が一機でも、新宿の高層ビルに旅客機が追突したら、どうなるのでしょうか。
ニューヨークのマンハッタンの9.11事件が生々しく横切ります。
単なる大騒ぎですまなくなってしまう。日本人の感情として、日本上空の制空権を返せ、という批判になるでしょう。
アメリカ軍が素直に返還するのでしょうか。アジアの防空システムから、返還できないと言えば、国民感情として、「はい。そうですか」となるのでしょうか。
むしろ、敵愾心から、横田基地を力で奪い返せ、というナショナリズムがわき起こる可能性も否定できません。自国の空が他国の軍隊に支配されているのは不合理だ、太平洋戦争の終戦が未処理だ、侵略されたままだ、屈辱だ。
歴史認識からすれば、被害者意識が1945年から、さらにさかのぼる可能性もあるかもしれません。
☆
第二次世界大戦が終わり、東京裁判が行われた。A級戦犯で、満州(まんしゅう)事変(じへん)の首謀者(しゅぼうしゃ)だった石原莞爾(かんじ)が『戦犯第1級のペリーを呼んで来い』と放言します。
まわりのアメリカ記者がなぜか、と問います。『鎖国主義で結構(けっこう)だと言っているのに、ペリー提督が平和日本を脅(おびや)かして、世界の荒波のなかに曝(さら)してしまったからだ』と語り、あ然とさせました。
日本は明治時代から教育で、ペリー砲艦外交(ほうかん・がいこう)に屈して開国させられたと教わっています。そして、日米修好通商条約という不平等な条約を結ばされた、と被害者意識を植え付けられてきました。
日露戦争に勝ったのに、アメリカの仲介でロシアから賠償金が取れなかった。ワシントン軍縮条約で屈辱(くつじょく)をうけたうえ、日英同盟が破棄させられた。日独伊三国同盟、満州国の建国すべてにわたって、アメリカは反対する。
満州問題からアメリカは仮想敵国(かそうてきこく)となってきた。国際連盟脱退におよび、アメリカの石油禁輸から、ABC経済封鎖された。
アメリカが日米交渉でハル・ノートを示し、満州事変以前にもどせ、と迫ってきた。もはやアメリカに言われるままになっていられない。「国民総意で、やるしかない」、「日米戦争は宿命だ」と結びついたのです。
明治以降の日本人は、幼少のころから、アメリカにたいする被害者意識が教え込まれてきたのです。それは石原莞爾(かんじ)のみならず、軍人政治家、軍人、国民の一般的な認識でした。当初、国民の殆んどが米国との戦争に歓喜しました。
現代でも、同一史観から、真珠湾攻撃はやむを得ない戦いだったと考える人は多くいます。さらには戦争を早く終わらせるためだと言い、東京大空襲、広島・長崎の大量の民間人を無差別に殺した。アメリカ流のていのよい口実だ、と批判の目をむけるひとは少なからずいます。こうした歴史的な被害者意識が、日本人の心の奥底に現存しているのです。

戦後の74年間の日米は蜜月でも、羽田空港への新ルートで大事故でも起これば、160年前のペリーの砲艦外交で蹂躙(じゅうりん)されてから、米国の言われるままだ。横田基地を力で奪い返せ、自衛隊をつかえ、安保条約の破棄だ、と一気に結びつきかねない。
ひとつ間違うと、火が点きやすい日本人の気質です。ナショナリズムが国論になってしまう。こうした被害者意識の歴史認識をしておかないと、危険です。
自衛隊は動かずしても、一般人が横田基地に侵入する。米軍が阻止する。日本人が実弾で射殺される。わずかな期間で、国内の騒擾(そうじょう)が、沖縄、岩国に連鎖し、政府の対応しだいで、戦争に発展しかねないのです。
北方問題でも、ロシアとの戦争を謳(うた)う代議士がいます。辞職もせずに、議席をもっています。
政治は民のためにある。国民の財産と生命をまもる。そのためには外国と戦争しないことです。危機を予測し、早めに手を打っておく。それが利巧な政治です。
日本の上空の制空権は、日本に返却してもらう交渉は始めておく。アメリカで、大統領とゴルフをしながらでもよい、本気で、この問題に取り組みべきです。
「歴史は繰り返す」この格言は肝に銘じるべきです。東京で、制空権の奪還問題で、米兵と流血事件を起こしてからでは、手遅れになる危険性がとても高いのです。
ひとつ航空機事故から、日米の歴史が一気にペリー提督の黒船まで戻らないためにも、強国のアメリカでも、主張すべきものは主張する。
それが政治家がよくつかう、政治に命をかける、ということばの実行です。