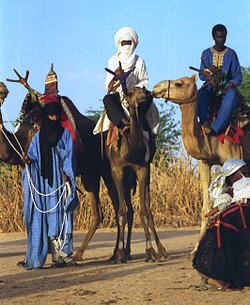汁かけごはん 金田 絢子
昭和44年6月30日の日記には、
「おとといパパが、金曜日の、多分お酒が原因で具合を悪くし、無理して出かけた銀行からはやく戻り、土曜日は夕刻まで大騒ぎだった」
ではじまる。
近くのY先生に来ていただき、注射をしたり、くすりを出してもらったことはなんとなく覚えている。
どうやら快復した夫は、月曜日、パンがゆを食べて出勤したらしいが、次に記してある当時8歳の長女と夫の会話は記憶にない。
「子供でもないのにあんなもの食べてるよ。おつゆをかけて食べちゃいけないというくせに、パパだってそうやって食べてるじゃないの」
「かけてるんじゃないよ。牛乳の中にパンを入れたんだ」
「私だってそういうふうにすることあるよ、おつゆの中にごはんを入れて食べることあるんだから」
遡って41年4月11日の日記にも、これに似た会話の場面が記されている。いずれも、もともとお味噌汁をご飯にかけて食べるのを、夫が快く思わないのに依っている。
夫に言わせれば、お行儀が悪いという訳である。私は、お味噌汁をかけて食べるのを、咎められずに育ったので、娘がそうやって食べても奇異には感じなかった。
この話を最近になって美容院で、若い女性美容師にしたら、
「お味噌汁をごはんにかけて食べるとホントにおいしいんですよね」
いかにも感に耐えないといった風に言ったので私は嬉しくなった。
常々、私は朝食に昨夜の残りごはんをあたためて、納豆をかけて食べる。
夫が亡くなってから、夜お味噌汁を作ったりするとつい二人前になる。朝、なべにのこったのをあたためなおし“あ、やっぱりかけよう”と妙に張り切ってしまう。
辞書でみると、
①汁かけ飯―味噌汁などをかけた飯。
②ごはんの上に具をのせ、だし汁をかけたもの。とある。
②の方がお行儀のよい感じがする。
夫は、食事の作法が特別よかったわけではない。
姑が「絢子さんと結婚するんだったら、結婚前に今少し、食べ方をしつけるんだった(姑は私をいいところのお嬢さんと思いこんでいた)」と言ったのを覚えているが、私がお味噌汁をかけるのが好きだなんて知らなかっただろう、と思うとおかしくなる。
見合いにしても恋愛結婚にしても、相手の生活習慣など、共に暮らして初めて知ることばかりである。
私は、結婚したてのころ、残りごはんをおじやにしたことがあった。

二、三日何気なくつづけていたら、夫は「いい加減にしてくれ」と腹を立てた。
まだ電子レンジが出はじめのころで、自宅のアパートにはなかった。暖めるかわりに、おいしいおじやにしたのに機嫌を悪くされてびっくりした。
夫婦は、相手のやり方、思考に戸惑ったり、共感したりしながら絆を深めていく。いつも夫は、私の意志を尊重してくれたものだった。
これからもつい、お味噌汁は二人前できてしまうだろうが、“汁かけごはん好き“としては、なんら問題のないところである。