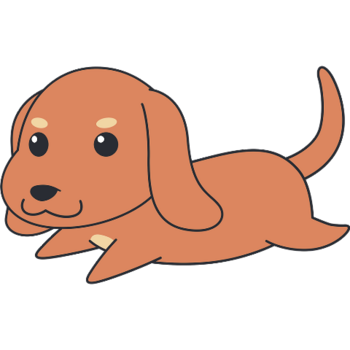働かないアリ 廣川 登志男
最近、俳優西田敏之さんの代表作である「釣りバカ日誌」を観た。主役のハマちゃん(西田敏之)と、勤め先の社長であるスーさん(三國蓮太郎)のコンビが絶妙で面白い。「フーテンの寅さん」と肩を並べる国民的人情喜劇だ。
このハマちゃんは、鈴木建設(株)のうだつの上がらないサラリーマンだが社内の雰囲気づくりに欠かせない人物として登場する。
真面目で、趣味の釣りは名人級。さらに、愛妻や多くの友人に囲まれた幸せ者だ。考えてみると、会社には得てしてこういった人物がいる。
居るだけで、仕事場が明るくなり、嬉々としてみんなが働く。仕事は二の次だが、何か問題が起こっても持ち前の明るさでいつの間にか解決してしまう。
普通に給料をもらえるならそういう人間になれたら良いなと、サラリーマンなら一度は憧れたことがあるのではないだろうか。これで給料がもらえるなら万々歳だ。
しかし、実態として社会に認められるだろうかと心配になる。
2、3年前だったと思うが、タイトルが「働かないアリに意義がある」という新聞記事があったことを思いだした。
タイトルの面白さと、「ハマちゃん」から「働かないアリ」を連想したのだろう。記事の内容はあまり覚えていなかったが、何となく興味が湧いてインターネットで調べてみた。
すると、思いもよらず、新聞記事と同じタイトルの本が見つかった。著者は長谷川英祐氏とある。
紐解くと、まず、アリやハチは女王を中心とした巣を作り、社会生活を営むとある。こういう昆虫類を「真社会性生物」と記されていた。
更に読むと、次からが仰天の世界だった。
なんと、巣のなかにはメスしかいないのだそうだ。
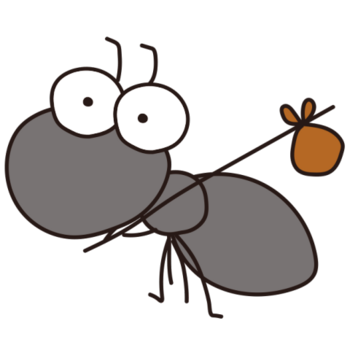 アリの世界で言えば、女王アリ・働きアリ・兵隊アリはすべてメスだと書いてある。ではオスはどこにいるのだろう。
アリの世界で言えば、女王アリ・働きアリ・兵隊アリはすべてメスだと書いてある。ではオスはどこにいるのだろう。
子孫を残す役割の女王アリは、オスと交尾して精子をもらわなければならない。驚いたことに、女王アリが交尾をする短い期間にだけオスとして卵から生まれるとある。
オスの寿命は1ヶ月ほどで、1回の交尾以外は何もしない。
さらに、女王アリは、長い一生の間にメスの卵を産むのに必要な量の精子を多くのオスから受け取ると交尾を終えてしまう。
一方、交尾を終えたオスは直ぐ死んでしまうし、まだ交尾をしていないオスは、厄介者として餌も与えられずに巣から追い出され死んでしまうのだそうだ。
なんと哀れなオスだろうか。アリに産まれなくて良かったと思うのは、私ばかりではないだろう。
こうして多くの働きアリや兵隊アリが巣の中に棲息する。ある学者が、巣の中で仕事をしているアリの数を調べたら全体の約3割しかいないとの結果を得た。
すなわち、7割のアリが何もしていない。このデータはある瞬間の状況を調べたものなので、著者らが大変な努力をして観察した結果、1ヶ月以上の期間でも約2割のアリは仕事を一切していないことが判明したという。
これはどういうことなのだろう。最後まで読んでわかったのだが、「働かないアリ」を字面通りに読んではいけないということのようだ。
エサ集め、幼虫や女王の世話、巣の修理、あるいは他の働きアリへのエサやりにくわえ、突発的な仕事もある。例えば、セミなどの大きなエサを見つけると多数の運搬アリが必要になるし、他の巣のアリに横取りされないよう早く自分の巣穴に運ぶための動員ということもある。
我々が子供時代にやった、アリの巣穴に土をかけて入り口を塞ぐなどはアリにとって大変な事故で、直ぐに修理するための動員もあるだろう。
だから、全員が一つのことに対応していたりすると、別の緊急事態が発生しても対処できなくなってしまう。くわえて、アリにも過労死がある。全員が休む間もなく働きすぎると一斉に死んでしまう。だから、適当な余力を持つために、「働かない『働きアリ』」の存在が重要になってくる。
こんな疑問もある。アリの世界には、指示を出す中管理職という階層がない。それなのに、動いたりじっとしていたりと個体間で差がある。
実は、ある事態に遭遇すると、どの程度のレベルでそれに反応するかが個々のアリで異なっているということが、昔からの経験でわかっていたらしい。さらに、この反応レベルの差が遺伝子レベルで決まっていると、多くの研究成果からわかってきたと著者らは書いている。
以上のことは、著書のほんの一部の紹介だが、最終的には「進化論」にまで結びついていた。
ここまで来ると、私の理解の範疇から大きく外れてしまっていて手に負えない。だが、こういった自然界の生態研究から、今流行りの『組織の多様性(ダイバーシティ)』に繋がってくるから不思議だ。
ハマちゃんから思い出した「働かないアリ」に関連して多くのことを学んだ。昆虫の世界でも「働かないが重要な存在」があると知り、会社のなかで特別な存在になっている「ハマちゃん」が認められた気がして、ホッとしている。
イラスト:Googleイラスト・フリーより
【了】