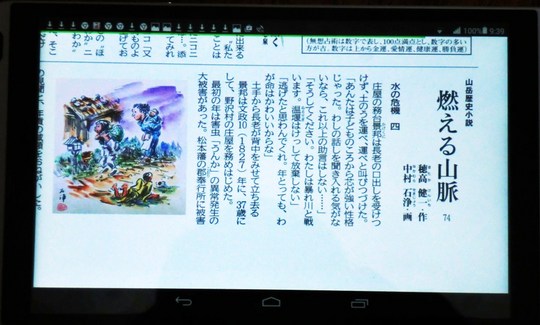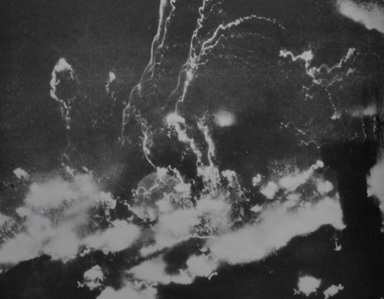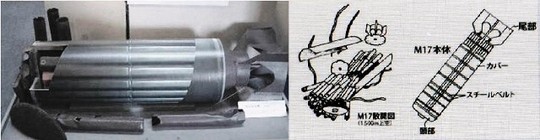西沢溪谷の一周、10キロ。秘蔵写真の発掘ほどでもないが?
5月29日の写真がある。このころの西沢溪谷は新緑だった。いまは夏山シーズンに入った7月初旬だ。
掲載のタイミングを逃せば、まずは見聞に価しないものだ。
しかし、10年来にして、初の20代の女性が加わった。われら登山隊としては歴史的なできごとだ。その写真を封印することはできないぞ。
「さあ、のぼろ。行こう」
先頭はむろんリーダーだ。
西沢溪谷の登山口で情報を得ようと、バス停から徒歩5分で、まずは茶屋に入る。
「ほんきかよ。はじめから、ルートくらい情報を持ってこいよ」
ヨモギ持ちを食べ、むヨモギ茶を飲みながら、地図を広げる。
10年経っても、この登山隊は進歩がないな。
登山というほど険阻な道でもない。それでも、明瞭な案内図がある。
遭難事故など起こしそうもないルートだ。
最悪の事故は、転倒の捻挫ぐらいだろう。
なめてかかるなよ。
ひとり準備運動に余念がない。
行動に統一性がないのが、われら登山隊だ。
「個人の意志の尊重」
と言ってもらいたいな。
やっと、明るく笑顔で、新鮮な空気を吸いながら、西沢溪谷のルートに入る。
女性一人はいると、こうも張りきれるものなのか。
男は正直だよな。
吊り橋をさっそうと渡る。
「怖くなんて、ないさ」
渡り終わると、そう言うんだよな。
集合写真を撮ってもらおう。
相手は快く引き受けて、笑顔で、シャッターを押してくれる。
よく見ると、右端には中近東の得体のしれない人物が写っているじゃないか。
たのむ相手が悪かった。
あきらめて、 記念写真はこれでがまんしよう。
西沢溪谷は、多彩な滝の連続だ。
これは良いぞ。
そう思いきや、カメラ目線をむけてくれる。
「あのな。滝を撮りたかったんだ」
これが見返り美人だったら、いいのにな。
「滝って、渓谷へ下るんじゃないの。なぜ登るんだ」
そろそろボヤキが出てきたぞ。
渓流沿いの平たい道にでれば、
「はい、チーズ」
こんなポーズもできる。
都会から離れたんだ。
新鮮な空気だ。
森林浴だ。
もっと胸を張って、楽しく行こうぜ。
野辺の送りじゃないんだから。
滝はスローシャッターで撮るんだよ。
手ブレをしない。
脇を固めるか、なにかしら三脚替わりを見つけると良い。
あれこれ教えるのは簡単。だけれど、やっては見せてくれなかった。
その調子、その調子だよ。