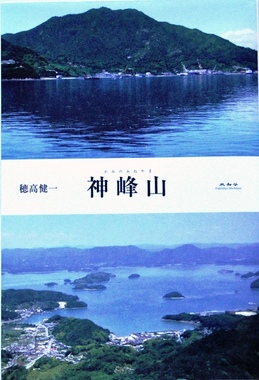富士山は雲の中だった大蔵高丸(1770m)=大久保多世子
1 登山日 :2018年6月9日(土)晴れ
2 参加メンバー : L佐治ひろみ、栃金正一、武部実、中野清子、開田守、金子直美、大久保多世子
3 コース :甲斐大和駅 ~ 湯ノ沢峠登山口 ~ 湯ノ沢峠~大蔵高丸 ~ ハマイバ丸 ~ 米背負峠 ~- 大谷ケ丸 ~ コンドウ丸 ~ 大鹿山分岐 ~ 景徳院 ~ 甲斐大和駅
8:40 甲斐大和駅に集合する。予約してあったタクシーで約20分、湯ノ沢峠登山口に到着した。中止もあり得る雨予報だった。だが、終日最高のハイキング日和になり、緑を満喫した爽やかな1日になった。
降車するなり、春ゼミの大合唱と、ウグイスの鳴き声が迎えてくれた。落ち葉が柔らかくなった山道は、足に優しく歩きやすい。
沢沿いに歩いたりクリンソウを愛でたりして、1時間で到着した避難小屋は、室内も綺麗に整えられていた。
その小屋からしばらく歩くと、尾根に出た。草原が広がっている。
可憐なスズランやキンポウゲの花が、目を楽しませてくれた。大蔵高丸は秀麗富士12景で展望は良いが、肝心な富士山は雲のなかに隠れたままである。
朗らかな健脚2人組に会い、集合写真のシャッターを押してもらった。
なだらかに起伏した尾根が続き、ゆるい登り下りを繰り返し、11:25にハマイバ丸に到着した。ここで昼食となった。
山頂の脇に「破魔射場丸」との表示があり、珍しい山名に納得できた。
山頂から少し下ったところは、露岩が散在した荒地で、破魔射場と呼ばれるそうだ。急な下りや笹やぶ・灌木帯を過ぎて少し登ると、【大きな岩=天下石】がある。
ここから先は広葉樹林帯が続き、木々の緑が一層美しい。下りきって、米背負峠に着き、正面の坂を登ると、大谷ケ丸に到着。先着の3人組が、「1時間ほど前に、すぐそこにクマが出た。」と教えてくれた。
若い男性とにらめっこを2回して、離れて行ったと話す。皆、緊張して顔を見合わせる。この山の西側から南アルプスも見えるそうだが、それよりクマ鈴を身に着けたり、話し声を大きくしたり……。幸い、熊に出会うことはなかった。
滝子山への分岐や滑りやすい急な下りを過ぎると、カラマツ林に変わる。地図には「防火帯に入らない」と注意書きがある通り、やや戸惑った。
右側に目印のリボンが5~6個ついていて、難なく進むことができた。大鹿山への分岐で、男性3人は山頂まで往復し、女性はそのまま下ることになった。
急な下りに時間がかかり、30分ほどで合流できた。大鹿山への往復は10分弱だったという。男性陣は皆、健脚揃いだった。
「間もなく景徳院だろう」
と思われる所。左にコンクリートで固められた山道、右に手すりのある急な細道があり、無標識なので全員で相談して、右に進んだ。だが、2か所も大きな柵で、塞がれていて大変であった。
二つ目の柵を過ぎてから、左の道が正解だったことが分かった。西日が強く、どっと疲れが出たが、傍らのヒメレンゲの群生が美しかった。
景徳院で休憩後、県道に出て、4:22のバスで甲斐大和へ向かった。
全体を通して、何か所か急な下りはあったが、最後まで歩きやすい柔らかな道の連続で疲れが少なかった。
ハイキングサークル「すにいかあ倶楽部」会報№226から転載