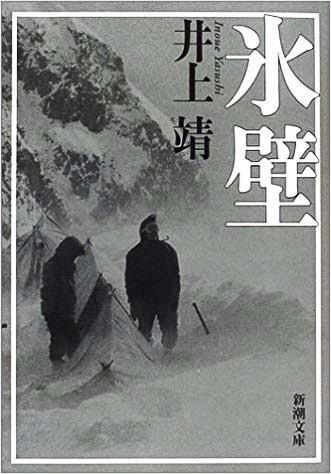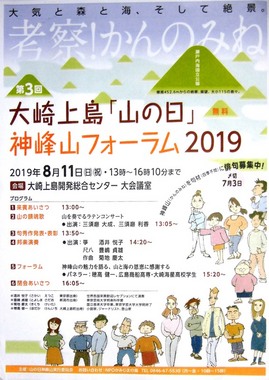山梨県・都留アルプス(尾崎山968m)=関本誠一
1.期日 : 2020年1月22日(水) 晴れ時々曇り
2.参加メンバ : L関本誠一、栃金正一、武部実、開田守
3.コース : 都留市駅~金毘羅神社登山口~富士山展望台~蟻山~白木山~長安寺山
~天神山~(尾崎山分岐A)~尾崎山~(尾崎山分岐B)~古城山~東桂駅
今回行くところは国内各地にある『なんちゃって…アルプス』の一つ。3年前に、地元山岳会と都留市が協力整備した標高500~600mの新しいハイキングコースだ。
途中で、下山できるエスケープルートはいくつもあり、体力や時間に合わせて家族・初心者でも歩ける親切なコース設定になっている。
富士急・都留市駅に集合8:45。
登山口まで徒歩で、金毘羅神社に到着9:05。
 ここからいきなり急登が始まる。落ち葉で滑らないように、慎重に登る。急登が終ると、最初のピーク、富士山展望台に到着9:20。
ここからいきなり急登が始まる。落ち葉で滑らないように、慎重に登る。急登が終ると、最初のピーク、富士山展望台に到着9:20。
山頂にかかっていた雲も取れ、富士山を眺めることができた。
ところどころに数日前に降った雪が残っている。発電所上部を通過して、尾根沿いに進む。蟻山、白木山、長安寺山と、小さなピークが続き、さらに少し下ったところにあるパノラマ展望台に到着した。
富士山は雲に隠れて見えなくなってしまったが、三つ峠山が存在感たっぷりで屹立している。
鍛冶屋坂の水道橋を通り過ぎ、天神山を過ぎと11:05。
元坂の水道橋の先に友愛の森(学校林)にある東屋に到着11:20。
ランチタイム(30分)をとった。そののち、千本桜植栽地を過ぎ、尾崎山分岐Aに到着12:25。
都留アルプスはミツマタ群生地など、尾崎山の中腹をトラバース気味に設けられている。われわれは尾崎山山頂を経て、都留アルプスにもどるルートをとる。
今までの登山道とは違って、荒々しいバリエーションルートで、残雪の急登が待っていた。軽アイゼンを装着して登る。だが、急すぎて滑る! 最低でも6本爪のアイゼンが必要だと痛感させられた。やがて、尾根に出たらなだらかな気持ちいい斜面になった。
下りは急斜面を慎重に下降し、尾崎山分岐Bに到着14:35。
ここで都留アルプスに合流した。このさき整備された道を進み、最後の登り、住吉神社を祭ってある古城山に到着15:10。
下山後は舗装路を東桂駅に到着15:40。
後半は大変だったが、反省会で盛り上がった。
ハイキングサークル「すにいかあ倶楽部」会報№246から転載