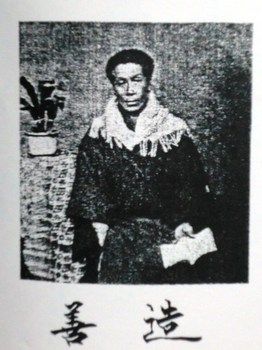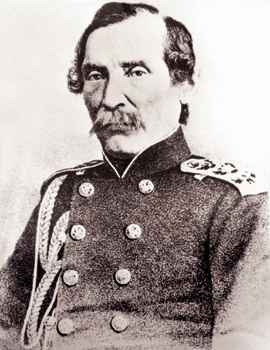「中房温泉」で発見。松本藩の隠された歴史=安曇野ブームの原点②
長野・あずみの市の取材協力者から、地元新聞のイベント情報の小さな記事がFAXで入ってきた。それは『拾ケ堰開削と十返舎一九の藤森家滞在』だった。10月25日(土)8時40分に松本市JR島内駅(大糸線)に集合である。
「拾ケ堰」(じっかせき)は私の歴史小説の主要素材の一つ。これまで車で何度か拾ケ堰を見ているが、一度は丁寧に歩いてみたいと思っていた。
「前泊で行こう」
夜に到着してホテル入りでは、勿体ない。そこで、24日(金)の早朝、いきなり自宅を出て新宿に向かった。
朝9時頃のタイミングで、中房温泉の百瀬(ももせ)社長に、午後の取材を申し込んだ。
「今日のきょうのアポだ、どうかな? もしだめならば、松本市文書館に出むく」
と択一の気持ちだった。
大糸線の最寄駅から乗った山岳バスは1時間余り。車窓の左右は山が燃えている紅葉の盛りだった。乗客はふたり。贅沢三昧な気持ちになれた。中房温泉に到着しても、標高は1500紅葉が周辺の山肌を染めていた。
文政4年に、庄屋だった百瀬茂八郎(ももせもはちろう)たち、5軒が中房に温泉宿を作った。松本藩が日本でも有数な「みようばん」の採掘をはじめたのだ。採掘の工夫たちが泊まる宿だった。
「ミョウバンは湯に溶かし、絹糸をほぐすと艶が出るんです。高く売れました」と百瀬氏は教えてくれた。
絹の着物は贅沢(ぜいたく)品だと言い、江戸幕府はなんども奢侈禁止令(しゃしきんしれい)を出している。江戸時代の三大改革など、奢侈禁止法につきる。
幕府から武士を含めて、贅沢(奢侈・しゃし)禁止を出す。倹約を推奨・強制する。その法令が出されても、その時だけで、直ぐになし崩しになる。人間は禁止されるほどに、贅沢品や嗜好品を手に入れたくなる。むしろ、絹の需要は却って高まるばかりになった。
松本藩はくるしい藩財政を救うために、幕府の目をかいくぐり、あるいは方針に逆らい、秘かに養蚕振興を推し進めていた。桑畑は目立つからつくるな。しかし、畦に鍬を植えれば、根が強くて畦の補強になる、と口実を設けた。藩は庄屋を通じて、「農商の女は夜なべして養蚕と織物に勤めよ」と命令を出している。

「松本藩は幕府に洩れないように極秘にして、通行手形がないと、中房温泉には入れなかったのです。麓の有明には関所が2か所ありました」
百瀬社長が語った。
ミョウバンは鉱石でなく、結晶なので、雨に溶けると教えられた。だから、湯に溶けて繭の糸をほぐすことができるのだ。絹の売買は一日市場(大糸線に駅名が残る)などで、藩外からきた商人によって取引がなされていた。
百瀬家の歴史をひも解くと、長野・三郷の小倉村の庄屋も兼ねていた。槍ヶ岳登頂の播隆(ばんりゅう)上人が登山基地にした村である。だから、播隆とも関わりが深い。
なぜ、播隆が信州に来たか。それには独自の解釈を持っていた。播隆が百瀬家に長く滞在したので、それなりの根拠があるのだろう。新田次郎氏も、「槍ヶ岳開山」の執筆前に、百瀬家に取材に来たと話されていた。
通説の播隆の槍ヶ岳登山ルートとは違った見解を持っていた。今後、それらも参考にし、検証していきたい。
【つづく】