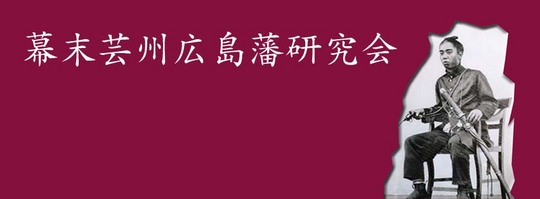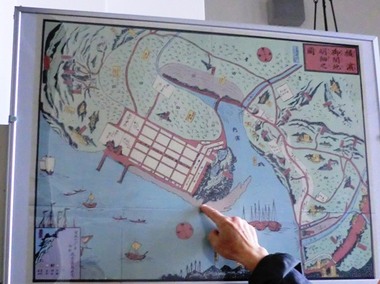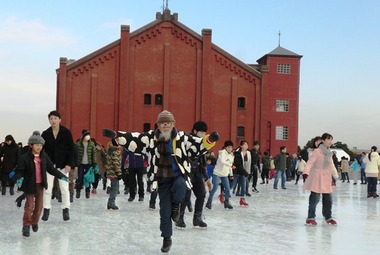言論弾圧をうけた高野長英が教える、ねつ造された歴史教科書(中)
天保10年(1839年)5月に、蛮社の獄(ばんしゃのごく)が起きた。名高い言論弾圧事件である。
田原藩の国家老だった渡辺崋山は自殺した。高野長英は永久牢獄の処分となった。しかし、牢獄で放火し、逃亡生活を続けていた。やがて見破られて殺された。
高野長英の『戊戌夢物語』は幕府批判をかわすために、あえて夢物語として、辛辣(しんらつ)に書き綴ったのだ。
その内容の一部を紹介してみたい。これは中国でアヘン戦争がおこる2年前に書かれたものだ、という認識で読まれると、徳川時代の海外情報力がわかる。

鎖国だから海外情報は皆無に近い、と思われている人は、なぜ、学校教育で、ここまで教えてくれなかったのか、とつよい疑問をおぼえるだろう。
高野長英著『戊戌夢物語』(現代訳)
「イギリス国は、オランダの王都のアムステルダムから180里(720キロ)ほど離れている。気候は日本よりもやや寒い国。人口は1770万6000人。イギリス人は敏掟な身のこなし、理解や判断が早く、物事の勉強を怠らず、文学に勤め、工技を研究し、武術を練磨し、『民を富まし国を彊(つよ)くしていることを第一の努め(目標)としている。
イギリスの沿岸は浅瀬が多く、外寇が入り難く、近年のナポレオン侵攻も、国民は戦火をまぬがれた。首都のロンドンし繁栄し、町並みが美しく、人家が密集し、人口はおよそ100万人。海運の都合がよい立地で、諸国との交易の中心となっている。
諸国に航海し、未開の土地で植民を行い、未開の原住民を指導し、服従せしめている。いまや外国の支配下の人口は7424万人で、イギリス本国の4倍にもなる。
① 北アメリカという国(カナダ)
② 北アメリカと南アメリカの中間にある、西インド諸島。
③ アフリカ州
④ 日本の極南にある、新オランダ(オーストリア)。
⑤ 南アメリカのブラジル。コイネア(ガイアナ)およびカルホルニア付近。
⑥ 天竺(インド)
⑦ インドのムガールとい、雲南、暹羅(シャム)の南部の地域。
⑦ 日本近海の無人島(小笠原)より南の諸島。
イギリスは軍艦を利用し、1隻につき4、50門の大砲(石火矢)を備えて、それぞれに役人をさしむけて支配している。軍艦の総数は、2万5860艘。役人は都合17万8620人、下役は40万6000人、ほかに水夫、雑役などを合わせると、100万人ほどになる。
かれらの航海術はことのほか熟練しており、外国への拡大と交易の道が旺盛にして盛んになっている。
イギリスは支那(シナ)と前々から交易し、広東のそばに土地を与えられて商館を営み、総督や役人を駐留させている。南海諸島やアメリカの産物を数十艘に積んで、広東に輸送いたし、もっぱらお茶と交換し、それを本国・イギリスに送っている。
イギリスは雲南、シャムのあたりにも領土を持っており、これが支那の属国と境を接しており、このあたりの住民が騒乱を起こし、国境を越えて、交戦することが時々ある。

イギリスと中国との交易が盛んになるほど、ポルトガル、オランダは自然と衰退ぎみになってきた。そこでかれらは色々と清国に告げ口をしたり、誹謗(ひぼう)したりしている。
清国はそのまま誹謗を信用している。しだいにイギリスへの嫌悪感が拡大し、双方の交易量と荷捌きが不振に陥ってきた。そのうえ、乾隆という皇帝の頃から、清の未払い勘定が日増しに増加してきて、いまやイギリスの清との交易は完全に行き詰っている。
イギリス本国でも、広東貿易を完全に中止するべきだという意見が出てきた。片や、イギリス本国では近年お茶を楽しむことが流行し、喫茶が大衆化した。
イギリス領の南海諸島の島やインド、アメリカのお茶は多く産出する。だけれど、品質が支那に比べてはるかに劣る。広東貿易をやめれば、良質のお茶が入らず、国民への迷惑に及んでしまう。
イギリス政府は清との関係改善を図るために、使節を派遣する。乾隆帝に子(嘉慶帝)が生まれたので、その誕生をお祝いし、貢物を北京の朝廷に献上する名目ができた。
イギリス政府は人選の結果、ロード・マカートニーなる人物を選んで、彼を正使として清に向かわせることに決めた。清は天文学・医術・物産学が未熟なので、これらの学術に精通した者も選んで同船させている」
こんなにも優れた情報力が日本にあったのだ。まさに、イギリスと清国と戦争状態に突入しかねない、不穏な空気が克明が高野長英の書物に明記されているのだ。