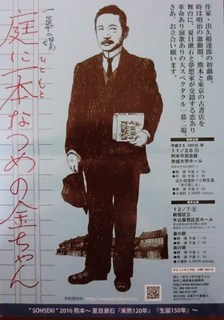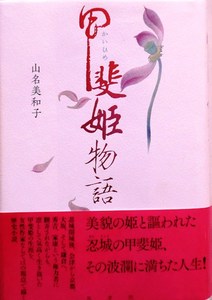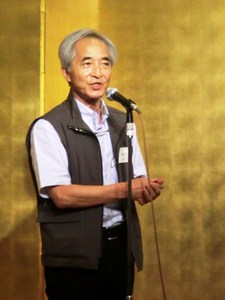「特定秘密保護法」言論・報道の自由を奪うと、戦争の道 ② 吉岡忍
市民は国の多くの情報に接する権利がある。政府は透明性をなくしてはいけない。権力が腐敗するように、秘密主義は社会を腐敗させる。むかしもいまも、自由な報道と私たち民衆の血液なのだ。
政府や官僚は秘密保全の過剰な強迫観念から、みずからの行動を隠し、あいまいにしている。「特定秘密保護法案」は、政府の秘密を膨張させ、市民の知る権利を奪うものである。
11月24日、東京・文京シビック小ホールで、『特定秘密保護法に反対する 表現者と市民のシンポジウム』が開催された。司会・進行役の篠田博之(『創』編集長)さんが、2番手として、吉岡忍(作家・日本ペンクラブ専務理事)を指名した。
 第一次世界大戦の後、言論表現の自由がなければ、それぞれの国家が勝手なことを言い、互いに憎しみ合って、戦争に及んで行く。こうした歴史的な反省のなかから、作家、詩人の集まりである「国際ペン」(本部・ロンドン)が誕生した。
第一次世界大戦の後、言論表現の自由がなければ、それぞれの国家が勝手なことを言い、互いに憎しみ合って、戦争に及んで行く。こうした歴史的な反省のなかから、作家、詩人の集まりである「国際ペン」(本部・ロンドン)が誕生した。
日本も昭和10年に島崎藤村を初代会長として「日本ペンクラブ」が下部組織の一つとして発足した。現在は世界中に約150センターがある。
国際ペンのジョン・ラルストン・サウル会長、副会長、獄中作家委員会・委員長から、日本政府の「特定秘密保護法案」に対して憂慮する、というメッセージをもらった。(会場に配布)。
吉岡さんは日本ペンクラブが発足した、昭和10年のころの言論統制と弾圧に触れた。
「日本ペンクラブが発足したときには、すでに「治安維持法」は発動されていたし、新聞が戦争の後押しをする体制が出来上がっていた。多くの書き手が執筆禁止となった」
戦前、戦中の日本ペンクラブや作家は、あまり活動ができなかった苦い経験がある。
そうした反省に立って活動を続けている。「特定機密保護法」は危険な法律だから、日本国内だけでなく、国際的にも、この法案の危険性を訴えてきた。
アメリカの外交政策、国際戦略はいまや行き詰っている。アフガン、イラク戦争のとき、アメリカはヨーロッパ諸国を巻き込めた。しかし、シリアの問題でわかるように、ヨーロッパ諸国はもはやアメリカの外交政策に協力しない態度に変わってきた。だから、シリアでは軍事的な対応ができなかった。
アメリカにとって、いま一番言うことを聞いてくれるのは、おそらく日本だろう。日本は1945年の敗戦以来、朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラク戦争など、「基地を出せ」、「金を出せ」、「血を流せ」と言ってきたが、日本政府は一度もNOといったことがない。こんなに従順で使いやすい国はないだろう。
日米軍事関係の連帯を結ぶ、それには秘密保護法が必要だとアメリカから背中を押され、与党は突き進んでいるのだろう。
こんな背景も含めて、日本ペンクラブは各国の約150のペンセンターに、レターを送った。
「私たちは外圧をかけようとするのではなく、日本国内の危険な事実を伝えるものです。『日本政府がやろうとする、特定秘密保護法案は危険性があり、その反対運動に賛同します』という声明をもらっています」
アメリカには同じような法律があって、「スパイ法」が戦後すぐにできた。
1970年代にはベトナム戦争が起きた。ペンタゴンでは秘密裏にいろんな情報を集め、分析し、この戦争の勝ち目のなさとかを解析していた。
そもそもこの戦争はアメリカ軍がこいに挑発し、ありもしなかったベトナムからの攻撃をあったとして、大々的に世界に発表した。そのうえで、これらを懲らしめるために、ベトナムを攻撃するんだと言い、始まった戦争である。
ペンタゴン(アメリカ合衆国の国防総省)は、アメリカ軍がでっち上げた事実を調査し、秘密として保持していた。そこの公務員だったエドワード・スノーデン氏が、ベトナム戦争に関する機密文書『ペンタゴン・ペーパーズ』をワシントンポスト紙やニューヨークタイムズに渡し、それが報道された。
アメリカ国民自体が、とんでもない戦争だ、と知り得た。
世論が「こんな風にして戦争がはじめられたとは知らなかった。こんな戦争だったら、手を引くべきだ。すぐやめるべきだ。まだ続けるつもりなのか」と、長い間戦ってきたアメリカは国内から批判の手が上がった。国際的にも犯罪だとされた。
やがて、アメリカのベトナム介入の舵は切られ、アメリカ軍の撤退となっていった。
暴露したエドワードや新聞記者たちは、スパイ法で逮捕されて裁判を闘った。
「けれども、当時の司法はなかなか健全でした。スパイ法にあたらない、情報を流した側も、受け取った側も、連邦の高裁、最高裁でも無罪を言い渡した。おそらく、日本で「特別秘密保護法案」が成立すれば、おそらく逆転ホームランは起きないだろう。毎日新聞の西山記者のようになるだろう。いま、政府にノーというメディアも少なくなってきた。私は懸念しています」
吉岡さんは何としても、廃案にするべきだと強調した。