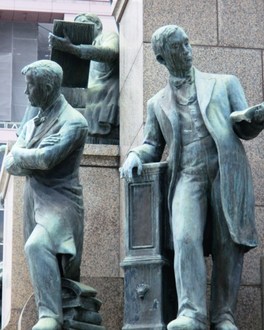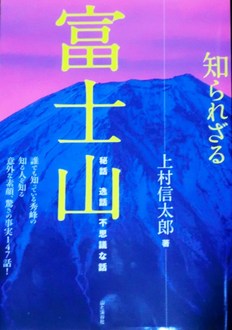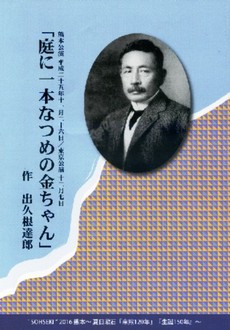中國新聞で、執筆中の歴史小説が紹介される=もう一つの戊辰戦争
中國新聞社の岩崎誠論説委員から、年初に「髙間省三の小説はいつ書きあがりますか。何月に出版ですか」と問い合わせがあった。執筆中であり、まだ初稿の段階で、すこし戸惑った。
予定は3月には脱稿し、5月には出版だから、その通りにお応えした。問われて、タイトルは未定です、と話す。小説執筆は仮題が必要なので、『二十歳の炎』としているが、活字になってしまうと、拘束されるし、出版社は売れるタイトルが必要なので、題名は言葉にしなかった。
 中国新聞1月16日朝刊で、自衛艦が広島沖で釣り船と衝突事故を起こし、一面トップを飾る、その日の文化欄(12)で大きく取り上げてくれた。『戊辰戦争と広島藩テーマ』が目に飛び込んでくる
中国新聞1月16日朝刊で、自衛艦が広島沖で釣り船と衝突事故を起こし、一面トップを飾る、その日の文化欄(12)で大きく取り上げてくれた。『戊辰戦争と広島藩テーマ』が目に飛び込んでくる
記事のリード文のみを紹介すると、
『明治維新に一定の貢献はしたが、薩長土肥の陰で新政府の表舞台に立てなかったのが広島藩だ。時代の変わり目にどう動いたかは地元でもほとんと知られていない。
その中で戊辰戦争に身を投じ、現在の福島県浜通り地方の戦場で21歳の命を散らした悲運の藩士がいたという。高間省三。ことし歴史小説の主人公になる』
という記されている。
同紙で書かれたように、幕末の芸州広島の活躍は殆ど知られていない。作家や研究者はいまなお少ない。理由は二つある。
ひとつは1945年の原爆は広島城の真上を狙った、城を取り囲む武家屋敷は廃虚で、史料は喪失した。致命的である。
もう一つは戦前の広島は帝国大学がなく、高等師範学校だった。だから、文部省の与えた教科書を教えるだけで、帝国大学のように、独自の芸州広島藩の研究がなされていない。結果として、活字になった幕末や戊辰戦争の研究資料が発表されていない。
薩摩、長州、土佐の豊富な史料に比べると、芸州広島の資料はあまりにも少なすぎる。実に、100分の1以下だろう。ある意味で、薩長土の資料からの小説にしろ、幕末紹介記事にしろ、それは書きつくされている。坂本龍馬ひとつとっても、大同小異、内容はほとんどおなじだ。
その点では、未開発の幕末広島史は、もう一つの戊辰戦争の意味合いが出てくる。従来の史観からすれば、まったく逆とか、途轍もない資料が見つかることもある。だから、「船中八策は偽物だ」とも断言できる。
大政奉還は広島藩が早くから推し進める。後藤象二郎が横取りした。それだけならばよいのに、後藤は広島の執政・辻将曹(家老級)にあることないことを告げ口した。それまで倒幕が薩芸で推し進んでいたけれど、薩摩と芸州広島の仲を裂く行為に及んでしまった。
広島藩・浅野家臣の船越洋之助が、辻の口からそれを知り、中岡慎太郎に抗議すると、
「貴藩に申し訳ないことをした。後藤象二郎を斬る」
と刀を手にした。
こうした史実も見つかる。
土佐側の書き手から、中岡慎太郎が後藤象二郎を斬る、という内容は中岡の日記からわかっていても、前後の流れが判らず、世には出してこないだろう。まして、龍馬・中岡暗殺にも絡みかねないし。
ちなみに、同席していた品川弥二郎(長州)が、おどろいて中岡を諭し、後藤象二郎暗殺を思いとどまらせたのだ。
戊辰戦争の会津追討にも、思わぬものが発見できる。「会津の悲劇」となると、学者や研究者や作家など、長州・世良脩蔵の傲慢さを中心にしてまわしている。基点がそこにある。
広島側の史料から見ていると、「えっ」というものが出てくる。京都・太政官(岩倉、有栖川)などは、送り込んだ公家、下参謀の世良などは早ばやと見捨た、第二次の行動に出ているのだ。
世良が殺されても、殺されなくても、関係ないじゃないか。そんな発見もある。
幕末の芸州広島はつねに新たな発見があり、おどろかされる。それは手垢がついていない歴史に携われる魅力でもある。小説の決められたページ数となると、素材が多すぎ、目移りがして取捨選択に苦慮してしまう。
中国新聞には大きく取り上げられていたし、もはや時間のかかる一次史料の読み込みよりも、ここらで小説執筆上の取りまとめにウェイトをかけよう、と決めた。