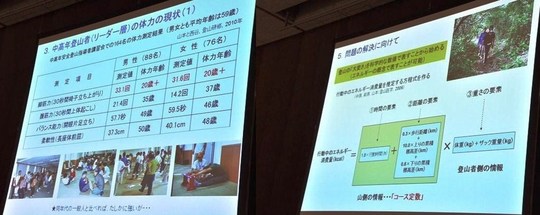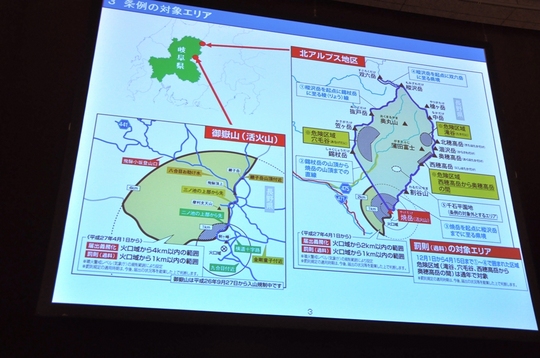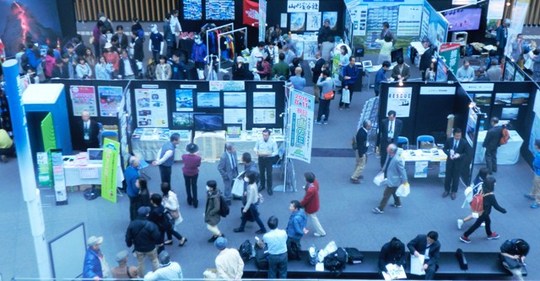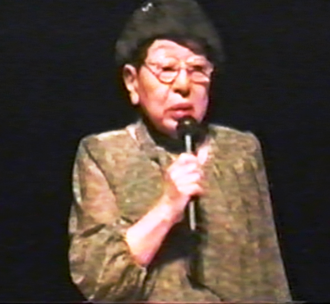「山の日」から、安全のための知識と方法(6)=東京・有楽町

3月29日は、日曜だが、国際フォーラムの会場には、山ガールも来ていました。トークショウを愉しんだり、登山用品関係をのぞき見たり、とても楽しそうな若者が多かった。それが特徴です。
石井弘之(ひろゆき)さんは、成城学園の中学校高等学校の校長である。
同校は1930年に、オーストリアからハーネスシュナイダーを招いて、スキーを学んでいる。「海の学校」「山の学校」は同校の伝統行事である。
中学1年生は「海の学校」で、生命の教育、心臓マッサージの実習、ADEの使い方などを学んでいる
中学2年生になると、240人が8班に分かれて、北アルプスに登っている。槍ヶ岳、白馬岳、唐松岳。大勢の生徒を安全登山させる対処法について語った。
教師はふだんの部活動、大山登山などを通して、個人の体力、集中力、指示に対する反応力など、総合的な判断から、一人ひとり挑む山岳を決めていく。この振り分が安全への第一歩である。
約100人の教員は、春と秋に、プロの山岳ガイドから指導を受ける。教員のなかにも、大学山岳部のキャプテンやマナスル登頂の経験者がいる。本隊に同行してもらい、次のリーダーとして学ぶ。
生徒への注意事項として、
① 走るな。 遅れると追いつこうとする。
② 振り向くな おしゃべりにつながる。
③ 荷物を谷側に置くな
④ 石をけるな
④ 手に荷物を持つな 両手を開かせておくことはとっさの対処になる。
前日に、登山に出かける装備で、登校させる。それぞれにチェックする。ヘアドライアーとか、缶詰とか、重いものを持ってくる生徒もいる。ザックの荷の計量を行う。
7月下旬は、このごろあてにならない。ゲリラ豪雨もある。後退する、勇気と決断が安全登山の要になる。「山の学校」のあとは、次年度に向けた反省会を行う。
 山本正嘉さん(鹿屋体育大学・教授)は、人間の運動能力の限界を引き上げるために、瞬発力、持久力、疲労、回復などに取り組んでいる。その成果をもとにスポーツ選手への教育や指導を行っている。
山本正嘉さん(鹿屋体育大学・教授)は、人間の運動能力の限界を引き上げるために、瞬発力、持久力、疲労、回復などに取り組んでいる。その成果をもとにスポーツ選手への教育や指導を行っている。
「登山は想像以上に、ハードなスポーツです。その認識が甘い人が多い。役立つトレーニングができていない」
そう述べたうえで、脚力が弱いとバランス能力と俊敏性に欠けてきて、事故につながります、とつけ加えた。
登山歴10年以上で、60~70歳代のベテランが事故を起こしている。
転ぶ事故が多い。つまずいたり、浮き石に乗ったり、踏み外したり、スリップしてバランスを失う。こうした事故は、全体の56%を占めている。
太郎平小屋に掲示された『最近の事故』から、足首骨折、大腿骨折、頭部座礁が多い、と事例で示す。
「病気による事故もあります。とくに山の登りで、心臓に負荷がかかり、突然死が起きています」
心肺機能が弱いことにも起因しています、と補足した。
山本は「運動の強さ」を11段階に分けている。
1レベルは座る、立つ、入浴、車に乗る
5レベルはかなり速く歩く、野球、ソフトボール、
6レベルは、ハイキング、ジョギングと歩行の組合せ、バスケット、水泳
7レベルは、無積雪期の登山、サッカー、テニス、スケート、スキー
8レベルは、雪山・岩山、ランニング(分速130m)、水泳(中くらいの速さ)
10レベルは、柔道、空手、ラグビー
11レベルは、速く泳ぐ、階段を駆け上る
【写真の上で左クリックすると、2倍の大きさになります】
安全登山のためにも、ふだんのトレーニングが大切である。山本さんは図表で示した。、
飯田肇(はじめ)さん(富山県・立山カルデラ砂防博物館学芸課長)は、「自然と危険を考える」という面で講演を行った。
『登山には4つのキーワード』
①身体の準備
健康ですか。トレーニングしましたか。よく眠れましか。仕事や勉学の疲れはありませんか。
②計画立案
まず地図を用意しましょう。どこに行くのか。どのくらい登り、下りがあるのか。逃げ道はあるのか。
③忘れ物はないか
レインウェア、防寒具、ヘッドランプなど、絶対に忘れてはいけないものをチェックしましょう。
④登山届
山で最も大切な安全対策です。
『高さと風』
高さを増すほどに、風が強くなる。規則性がないので、予測が難しい。山岳は地形によっては、強風になる。
冬はジェット気流の基軸が南下するので、とんでもない強風になることがある。
瞬間風速は平均風速の1.5~3倍になる。