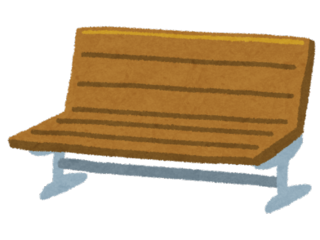近 年 に な い 大 型 の 台 風 らしいので、 我 が 家 で は 雨 戸 を 閉 め たり 、 庭 の 飛 び や す い 鉢 を 室 内 に 入 れ た り 、 台 風 へ の 備 え を し た 。
風 雨 は 夕 方 か ら し だ い に 強 ま り 、 夜 に な る と 暴 風 雨 と な っ た 。
家 の サ ン ル ー ム の ガ ラ ス に 、 庭 の 木 の 枝 が 勢 い よ く 当 た る 。 時 おり 、 ゴ ー ッ と い う 音 が し て 強 風 が 吹 き 、 ミ シ ミ シ と 家 が 揺 れ る 。「 家 は 大 丈 夫 だ ろ う か 」 眠 れ ぬ ま ま 不 安 な 夜 を 過 ご し て い る と 、夜 中 12 時 ご ろ 、 突 然 電 気 が 消 え た 。 真 っ 暗 な 中 、 懐 中 電 灯 を 探し た 。
「 こ ん な 強 風 な の だ か ら 、 電 線 が 切 れ る こ と も あ る だ ろ う 。 明 日に な れ ば 台 風 も 去 り 、 復 旧 す る だ ろ う 」 私 は そ う 軽 く 考 え て いた 。
停 電 は 2011 年 3 月 の 東 日 本 大 震 災 後 の 計 画 停 電 以 来 で あ る 。
あ の 時 は た っ た 4 時 間 だ っ た が 、 何 も で き ず 、 寒 い 中 毛 布 に く る
ま っ て 過 ご し た の を 思 い 出 し た 。
今 度 は 夏 だ が 、 ク ー ラ ー を 入 れ る こ と もで き ず 、 窓 も 開 け ら れ な い の で 、 寝 苦 し い夜 だ っ た 。
2019 年 9 月 8 日 、 台 風 15 号 が 関 東 地 方 を 直 撃 し た 。 夜 が 明 け 、 窓 を 開 け て み る と 、 庭 の 木 々が 折 れ て 散 乱 し 、 サ ン ル ー ム の ガ ラ ス に は飛 ん で き た 落 ち 葉 が 至 る と こ ろ に 張 り 付 いて い た 。
外 へ 出 て 少 し 歩 く と 、 大 き な 木 が 折 れ て住 宅 に 倒 れ て い る 光 景 が 目 に 入 っ た 。 テ レビ は 映 ら な い の で 、 ス マ ホ か ら だ け の 情 報だ が 、 関 東 地 方 、 特 に 千 葉 県 に 被 害 が 出 て い る ら し い 。
近 く の 高 速 道 路 は 通 行 止 め で 、 一 般 道 は 大 渋 滞 。 電 車 も ス ト ップ し て 、 ど こ へ も 行 く こ と が で き な い 。 ま さ に 陸 の 孤 島 で あ る 。
そ れ で も 、 今 ま で の 経 験 か ら し て 、 こ ん な 状 態 は 丸 一 日 も あ れ ば解 消 す る だ ろ う と 思 っ て い た 。
ラ ジ オ で 聴 く 東 京 電 力 の 会 見 で も 、 最 初 は 1 ~ 2 日 の う ち に 復旧 す る だ ろ う と の 予 測 だ っ た 。 夜 に な り 、 真 っ 暗 な 中 、 外 の 灯 りに 気 が つ い た 。 窓 を 開 け て 空 を 見 上 げ て み る と 、 明 る く 光 る 月 が見 え た 。 街 灯 も な い 中 、 や け に 月 明 か り だ け が 目 立 っ て い た 。
二 日 目 に な っ て も い っ こ う に 電 気 は つ か ず 、 長 引 く 停 電 の ため 、 水 ま で 出 な く な っ て し ま っ た 。 丸 二 日 経 っ て 、 も う 冷 蔵 庫 の中 の 氷 も 保 冷 剤 も す べ て 役 に 立 た な い 。 冷 蔵 庫 内 の 生 も の は す べて 処 分 し な れ ば い け な い 。 ト イ レ は 風 呂 に 溜 め た 水 で 流 し た 。 食事 は カ ッ プ 麺 な ど で 済 ま せ た 。
テ レ ビ が 見 ら れ な い な ど の 生 活 の 不 便 さ は 何 と か 我 慢 で き たが 、 暑 さ で 夜 も 熟 睡 で き ず 、 精 神 的 に か な り 参 っ て い た 。
近 所 の 人 た ち の 中 に は 都 内 の 知 り 合 い の 家 へ 行 っ た り 、 ホ テ ルに 宿 泊 す る 人 も い た 。
停 電 三 日 目 と な り 、 心 身 と も に 疲 労 し て き た 。 水 は 出 る よ う にな っ た が 、 電 気 は ま だ だ 。 ス マ ホ を 充 電 す る た め に 、 車 で 30 分ほ ど の コ ン ビ ニ を 利 用 し た 。 こ こ は 断 水 だ が 、 電 気 だ け は つ い てい た 。 こ の こ ろ 、 道 路 は 開 通 し て い た が 、 今 度 は ガ ソ リ ン ス タ ンド へ の 渋 滞 が 始 ま っ て い た 。 暑 さ の た め 、 車 内 で 過 ご し て い る 人が 多 く な っ た か ら だ 。
ラ ジ オ か ら の 情 報 で 、 被 害 の 状 況 が だ ん だ ん わ か っ て き た 。 停電 は 千 葉 県 内 で 30 万 戸 近 く に な っ て い た 。 屋 根 瓦 が 飛 び 、 多 くの 人 た ち が 雨 漏 り で 困 っ て い る と 聞 い た 。 私 は 家 の 被 害 が な か った だ け で も 幸 運 だ っ た 。 そ う 考 え て 我 慢 し よ う と 思 っ て み る も のの 、 暑 さ の た め 、 う ち わ を 手 放 せ ず 、 う ん ざ り し て い た 。
以 前 住 ん で い た 海 沿 い の マ ン シ ョ ンを 見 に 行 っ た 。 自 宅 の 部 屋 は 大 丈 夫 だっ た が 、 自 宅 の す ぐ 下 の 部 屋 は 、 ガ ラス が 粉 々 に 割 れ て い た 。 こ こ に 住 ん でい れ ば 、 も っ と 大 変 な こ と に な っ て いた か も し れ な い 。
停 電 三 日 目 の 夜 に 、 再 び 東 京 電 力 の記 者 会 見 が 行 わ れ た 。 電 気 が つ く の を今 か 今 か と 待 ち 望 ん で い る の に 、 発 表 で は 、 被 害 が 思 っ た よ り ひ
ど い の で 一 週 間 か ら 十 日 ほ ど か か る と 言 う 。 私 は 絶 望 し た 。
「 こ ん な 生 活 が 続 く な ら 、 ど こ か へ 逃 げ 出 し て し ま い た い 。 明 日
こ そ は 友 人 の 家 に で も お 世 話 に な ろ う 」
そ う 思 い な が ら 、 う ち わ を 持 っ て 布 団 に 入 り 、 再 び 寝 苦 し い 夜が 始 ま っ た 。 数 時 間 経 っ た 時 、 か す か に 何 か の 電 子 音 が し た 。 それ は ど こ か で ス イ ッ チ が 入 っ た よ う な プ チ ッ と い う 小 さ な 音 だ った 。 そ れ と 同 時 に テ レ ビ の 電 源 の 赤 い ボ タ ン が 光 る の が 見 え た 。
「 電 気 が つ い た ! 」
私 は 思 わ ず 叫 ん だ 。 電 気 が つ く こ と が こ ん な に も 嬉 し い と は 思 わな か っ た 。 思 わ ず 家 の あ ち こ ち の 電 気 を つ け て 回 っ た 。 深 夜 に もか か わ ら ず 、 隣 り 近 所 の 家 に も 、 次 々 と 灯 り が つ き 始 め た 。 皆 、考 え る こ と は 同 じ な の だ ろ う 。
私 の 家 の 近 く に は 大 き な 救 急 病 院 が あ る 。 そ の 病 院 の 自 家 発 電が 切 れ そ う に な っ た た め に 、 こ の 地 域 の 停 電 が 早 く 復 旧 し た と いう 話 を 、 あ と に な っ て 聞 い た 。
結 局、 停 電 は 丸 三 日 、 断 水 は 一 日 だ っ た 。 今 の 便 利 で 快 適 な 暮 らし の ほ と ん ど は 電 気 に 依 存 し て い る 。 電 気 や 水 の あ り が た さ 、 それ を い つ も 守 っ て い る 人 た ち の あ り が た さ を 、 今 回 の 台 風 で イ ヤと 言 う ほ ど 思 い 知 ら さ れ た 。