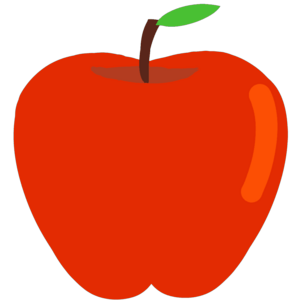眠れぬ夜の百歌仙夢語り<七十八夜> 望月苑巳
何が楽しくて野郎ばかり三人で飲んだのか分からない。
その時なぜかパンツの話になった。
オイラが「俺はトランクス派だよ。風通しがよくて蒸れないから」というと、髪の毛がすだれのY君がのたもうた。
「いやいや、断然ブリーフだね。締まりがあっていい。第一漏れないからな」
「確かに」
思わず頷いてしまったオイラはお漏らしジジイか。
そこで黙って聞いていたむっつり助平のK君に「おい、おまえはどっち派だ」と聞いたら胸を張って答えたね。
「それがどうした、俺は紙オムツ派だ」
心なしか目が虚ろだ。
そうだよなあ。気がつけば古希。古来稀なりという言葉にドキリとする。坂道を上がれば心臓が鯉みたいにバクバクする。後期高齢者という棺桶に片足を突っ込んでいるんだから。
神も仏もないとはこういうことか。
下ネタ続きで申し訳ないが、有名なエピソードを一席。いや、これは神かけて真面目な下ネタだ。
和泉式部といえば恋多き女として知られる。熊野詣に出かけた時のこと。本宮の近くまできたら、何と月のものが始まってしまった。不浄の身では参拝するわけにはいかない。
仕方なくその場から熊野権現を伏し拝んだという。
その時に詠んだ歌がある。
晴れやらぬ身にうき雲のたなびきて月のさはりとなるぞ悲しき
月のものまで詠んでしまうという、和泉式部の歌に対する情熱にはただ脱帽あるのみだ。さすがとしか言いようがない。しかもこれには後日談がある。
歌を詠んだ夜、和泉式部の夢枕に熊野権現が現われ
もろともに塵に交わる神なれば月のさはりもなにか苦しき
と歌を返してきたというのだ。これは「紀伊続風土紀」にあるのだが、伏拝という地名はここからきているという。ふうむ、伝説恐るべし。いや、神様も粋なことを言うもんだ。どうです、真面目な下ネタだったでしょう?
そんなことを書いたから罰が当たったのか、12月に入って人生初のインフルエンザB型にかかった。
「当選おめでとうございます!」
医者の結果を伝えるとマグロの奥さん、目をウルウルさせ、ここぞとばかりに娘と孫に一言。
「近寄っちゃダメ、口をきくのもいけないの、目を合わせたらおしまいよ。それだけでうつるからね」
俺は妖怪人間ベムか。おかげで一週間アルカトラズの独房生活を味わったぞ。
余談だが、昔読んだ朝日新聞のコラムに工藤雅世という人がこんなことを書いていた。
「私たちは他人と出会ったとき、緊張や警戒心から、無意識に相手との間にある空間を保とうとする。この空間を、心理学ではパーソナルスペースと呼ぶ」
そしてこのパーソナルスペースの距離は民族や文化によって違うというのだ。
確かにパリのカフェではテーブルが混みあった状態で配置されていても人々は違和感がない。アラブ人やラテン系の民族でもそうした傾向があるという。
一方アメリカ人やイギリス人は警戒心が強くスペースを大きく取るというデータがあるそうだ。日本人もこの部類に入るのかも(ただしテロが頻発する現代ではこれらのデータは信憑性に欠けるが)。
この大きさを知る「接近実験」という方法によれば女性は男性が近づいてくると大きなスペースを確保しようとするが、男性は逆に女性が近づいても大きなスペースを取ることがないという。
男はみんな下心があり、女性は「男はみんな狼よ」という歌(昔だから若い人は知らないだろうな)がある通り原始的な警戒心が感覚的に出るのだろう。
なぜこんなことを書いたかというと、家族とのパーソナルスペースについて考えてしまったからに他ならない。
さて無事に〝アルカトラズのお勤め〟を終えて久しぶりにアルコールにありついた。おでんをつまみにチビリチビリやっていると、今や安上がり制作のテレビ番組には欠かせない幻の温泉宿という番組をやっていた。
修験者が宿の裏で瀧に打たれている。
孫の樹が「源泉かけ流しだね」と言った。確かにその通り。むしろかけ流しというより垂れ流しと言ったほうが正しいかも。
気がつけばもう高校二年生。先日のテストで赤点があったらしい。頭抱えて
「ドツボだ~」
それも2科目だから
「ドツボのミックスジュースだ~」
「人生の交差点で轢かれた気分だろ。きっと赤信号だったんだよ」と慰め?たら「そんなところに信号機はない」とプンプン。
「少しは勉強して人間の見本になってみろ」といったら、それは「理科室にあるよ」だと。それは人体模型のことだろうが。
ああ言えばこう言う、社会に出ても口だけが達者な嘘つきな大人にはなってくれるなよ。
「ただいま~」
そこへ正月のお宿下がりで、すっかり太めになってしまった長女の綾夢姫が孫の明里ちゃんを連れて帰ってきた。
夫とうまくいっていないのか多少ノイローゼ気味か。玄関を開けていきなりマグロの女房殿に抱きついた。
「充電できた~」
そうか、バアバはバッテリーだったのか。しかも、家にいて分かったことがある。
この綾夢姫が「(娘の)明里はいくら食べても二時間経つともうお腹が空いたっていうのよ。凄く燃費が悪くて困っちゃう」とこぼすのだ。(知らなかったよ。明里は外車だったのか!)そりゃあ、母親に似たんだろう。早く気がつけよ。