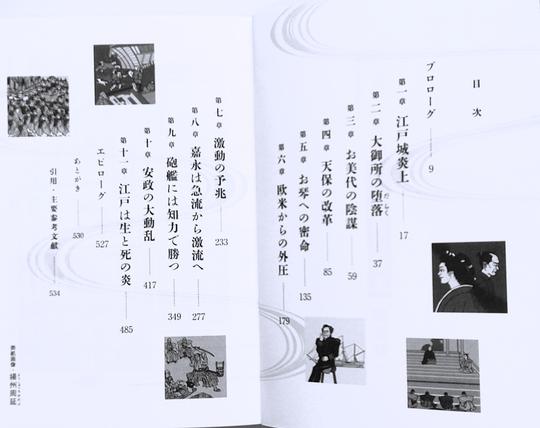「妻女たちの幕末」は、通説の裏舞台をよみとく内容が豊富である。①
新刊「妻女たちの幕末」は、どんな小説だろう、読者は本を手にしてまず目次をみる。ここに工夫を凝らした。
プロローグ~11章~エピローグまで、縦書きでならぶ。と同時に、新聞小説の挿絵(イラストレーター中川有子・298回)から抜粋して挿入している。
ビジュアルに、幕末のどんな内容が描かれているのか、読者には多少なりとも連想ができる工夫をしている。大奥一辺倒の小説ではないとわかる。
幕末史に関心がある読者は、きっとあの場面だなと想像も沸き立つ。
本文を読んでみないと判らないのが、女性が武士に手打ちになる挿絵だろう。「将軍家慶の側室・お琴が大工と不倫して処刑される」。ここらは知りたいところだな、と思うだろう。
*
徳川将軍に謁見の場は、絵が小さいけれど、これは13代徳川将軍・家定である。かれはとても有能で、数々の業績を残している。
ところが、明治政府には徳川幕府を卑下するするために、故意に家定を病身で無能扱いでこき下ろし、この背景には何があるのだろうか。
この家定は「5か国の通商条約」を3か月で一気に締結させる道筋をつくった将軍である。というのも、日米修好通商条約の締結を前に、老中・堀田正睦(まさよし)がみずから京都に出向いて、天皇から通商条約の勅許をもらう行動に出た。しかし、結果は膨大なお金を公家にバラまいただけで終わった。
将軍・家定は、京都から帰ってきた老堀田を外し、井伊直弼を大老にすえた。むろん、家定の思し召しであった。(彦根藩の井伊家の資料)
井伊は国学に陶酔する尊王主義者であった。
「天皇の勅許を待ってから、日米の通商条約を締結したい」
と家定に申した。
家定は外国通である。世界の流れをよく知っている。
「堀田が京都にいって朝廷や孝明天皇に説明したが、勅許が得られなかったではないか。何年先まで天皇の勅許を待つつもりだ。中国をみよ、インドをみよ、ベトナム、ラオス、インドネシア、近年ことごとく植民地になっているではないか。植民地になってから勅許をもらっても手遅れになるのだ」とかたくなに突っぱねた。
すると、井伊直弼が大老職の辞表を提出した(井伊家資料六)。
家定は辞表を受理せず、「これは日本の将来のために必要だ」といい、この日のうちに岩瀬や井上に日米通商条約の締結を命じた。こうして勅許なし通商条約の締結を押し切った将軍・家定である。外国奉行たちは将軍の意向だといい、5か国の言語が違う国と外交交渉をもってわずか3か月という超人的な技で「安政の5か国通商条約」を締結させたのだ。
そのさなかに、家定は急死した。(当時は毒殺されたとみなされた)。
安政の大獄の後、水戸藩の浪士が井伊大老を暗殺した。
ところで、家定・井伊が亡きあとも、開港・開国の流れは加速した。血で洗う尊王攘夷派さえも、海外との交流を止めきれなかった。幕府は、世界の流れから亡き老中阿部正弘が掲げた「富国強兵」をめざし、西洋の近代的な政治、軍事、商業、産業などを模範とすることにきめていた。万延、文久、万治、慶応と幕臣たちの英語、フランス語を習わせる。
かたや、旗本から抜擢した有能な人材を遣米使節にくりだす。留学生もくり出す。その数は数百人にも及ぶ。
長州ファイブというがわずか5人、薩摩もその数は19人、幕府の海外視察や留学生の足元にも及ばない。
幕府は留学生だけでなく、お雇い外国人を招聘し、横須賀に大規模な近代的な造船所をつくる。長崎に製鉄所を作る。築地には豪華なホテルを作る。アメリカには蒸気機関車と鉄道網の敷設を依頼する。近代化に突っ張りはじめた。
フランスには軍事教練の指導者を招き、歩兵、騎馬、砲兵の編成をする。
小栗上野之助などは、西洋流の群県制を樹立し、政治の近代化を目指した。
財政難の徳川幕府が困難な政治・経済上の条件の下で、西洋文明を取り入れることに鋭意努力し、新しい日本の建設の先駆者になったのである。
明治時代になると、下級藩士たちによる新政府が樹立したが、かれらには確固たる政治理念がなかった。そこで、幕府の近代化路線を引そのままき継いだ。
「明治から文明開化」と提唱するには、将軍・家定が先見の目がある外交通りの有能では困るのだ。「将軍は無能で、井伊が強引だった」という筋書きが必要であった。
*
ここで利用されたのが、春嶽の随筆「逸事史補(いつじしほ)」である。明治3年から12年に書かれたものだ。そのなかで、将軍・家定に冷遇された腹いせから、「平凡の中でも最も下等」 と嘲っている。
家定の継嗣問題が起きた時、春嶽は一橋派擁立しようと画策した。将軍・家定から罰せられ、謹慎・勅許となった。となると、憎き家定なのだ。
南紀派の勝利で13歳の将軍家茂が誕生した。若き将軍上洛を企画したのが春嶽である。それは長州藩・毛利敬親の建言によるもの。春嶽が京都に一足先に着くと、「天誅の血の世界」の光景があった。つまり、「将軍上洛は攘夷決行日を決めさせる」長州藩の陰謀のである。それがわかった総裁職の春嶽は、自身が計画した将軍上洛なのに、家茂をほっぼり、真っ先に京都から逃げて福井に帰った。これを知った大名たちも雪崩現象を起こし、京都から次々に立ち去った。
将軍・家茂は孤立し、窮地に陥った。
この前代未聞の春嶽の醜態にたいし、幕閣は怒り、春嶽の辞表は受理せず、処罰したのである。窮地に立つと醜く逃げまわり、さらに徳川家が瓦解寸前という重要な局面で、新政府側に寝返ってしまう。これが春嶽の実像だ。
随筆「逸事史補」を読めば、数多くの言い訳が羅列されている。幕閣を貶(けな)し、自分を高ぶって見せる、挙句の果てには明治政府の要人には美辞麗句のゴマをすっている。
故意に酷評した家定と、明治の三傑との評価の落差には、とても正常の知能とは思えない。春嶽はさすがに死に際において、良心が痛んだのか、「逸事史補はぜったい世に出さないで燃やしてくれ」と遺言した。
ところが明治の学者が、春嶽の遺言を無視したのだ。これは前政権の幕府を攻撃する格好の材料だといい、「幕末期の知られざる逸話」として、随筆・逸事史補を史実として悪用したのである。
そして、「家定無能だから、一橋派の擁立が正当だった」という筋書きをつくったのだ。それというのも、一橋派の面々が新政府の要人になったからである。
歴史小説「妻女たちの幕末」において、このように通説の裏舞台を克明に描いている。